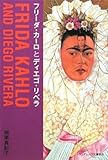読書日記「フリーダ・カーロとディエゴ・リベラ」(堀尾真紀子著、ランダムハウス講談社刊)
フリーダ・カーロとディエゴ・リベラ
posted with amazlet at 09.03.28
堀尾 真紀子
ランダムハウス講談社
売り上げランキング: 66662
ランダムハウス講談社
売り上げランキング: 66662
もう1年以上前になるだろうか。NHK衛星放送でメキシコの女性画家、故フリーダ・カーロのドキュメンタリー特集を見て、衝撃を受けた。
できれば目を背けたくなるような作品の数々に、驚きかつ揺り動かされるような印象を受けた。
知人の前衛画家・しばた ゆりによると、2007年に生誕100年展が開かれるなど、フリーダ・ブームはアメリカから日本へと波及し続けているという。
この本は、20数年もの間、フリーダ・カーロに肉迫し続けてきた堀尾真紀子の新作。新聞の読書欄で知り、図書館に購入申し込みをしに行ったら、閲覧書架に並ぶ寸前に借りることができた。
作者は、フリーダの波乱に満ちた生涯を、その作品に肉薄しながらたどっていく。
フリーダ・カーロは、子どもの時に小児麻痺を患い右足が不自由だったが、18歳ではじめてできた恋人と一緒に乗ったバスが事故に会い、手すり棒が子宮を貫通、脊髄、骨盤を骨折、生涯手術を繰り返す運命を背負う。
独学で学んだ絵の才能を、メキシコを代表する画家・ディエゴ・リベラに認められ結婚するが、ディエゴの派手な女性関係に傷つけられ、彼女自身も奔放な恋愛を重ねる。癒されることはなく一度は離婚するが、翌年には復縁。ディエゴに見守れながら、47歳で他界する。
フリーダの作品の軸になっているのは、自画像だと作者は言う。
「最初の自画像」(1926年)は最初の恋人・アレハンドロに贈られた。作者自身が現役の政治評論家である85歳のアレハンドロを訪ねて、2階の書斎に今でも飾られているのを確認している。
クールな表情にもかかわらず、全体から伝わってくるのは女性らしいたおやかな優しさと何かを懇願するようなメランコリックなひたむきさであった。あふれるような情感と甘い官能性と哀願と・・・。不思議な香りの立ちのぼる自画像だ
しかしフリーダの描く自画像は、次々とすさまじい〝自己暴露〟を重ねていく。
「ヘンリー・フォード病院」(1932年)は、6回の流産を象徴しているという。血管のような赤いリボンにつながった男児の胎児、傷ついた骨盤、苦痛を意味する万力のような機械・・・。
かってこのようなすさまじい裸婦像があっただろうか。・・・彼女のその独自の眼差しは、これまで決して描かれることのなかったテーマ、妊娠や堕胎、出産といった女性の生理までも画布にとどめてしまったのだ
「2人のフリーダ」(1939年)が生まれた背景は、ディエゴとの離婚だった。
自画像の右側は、ディエゴに愛されているときのフリーダだ。・・・一本の血管が延び、二人のフリーダの心臓へと繋がっている。・・・しかしその血管は左側のビクトリア朝衣装のフリーダの心臓を潤してはいない。左側の心臓はひからびた空洞と化している。なぜならこのフリーダはもうディエゴに愛されていないからだ
再婚後彼女は「いつも私の心にいるディエゴ」(1943年)を描いている。
衣装からのぞくフリーダの顔は、絶望をくぐり抜けたあとの安堵のも似たあきらめと、未だ醒めやらぬ葛藤とが同時に窺える。・・・ディエゴを独占しえない苦悩の解決としてフリーダは、ついに自分の額にディエゴを封じ込めたのだ
こんな自画像も残っている。「トロッキーに捧げた自画像」(1937年)は、恋人、トロッキーに贈られたもの。スターリンとの権力闘争に敗れたソ連の革命家、トロッキーは、共産党員だったディエゴに招かれてメキシコに亡命、フリーダと出会い、別れる。
いつもの醒めた自己凝視の鋭さはなく、自分に魅了された相手の心を、別れたあともつなぎとめておきたい意図が見て取れる。そこにはフリーダの自己陶酔と、自信に裏打ちされた誘惑心が垣間見えてくる
しかし、運命にほんろうされ、深く傷つけられるのはいつもフリーダだった。
ディエゴが、フリーダの妹クリスチーナと密通した際に描かれたのが「ちょっとした刺し傷」(1935年)であったし、十数回目の手術のあとの自画像が「小鹿」(1946年)だった。
鋼鉄製のコルセットまで装着しなければならなかったフリーダが1944年に描いた「ひび割れた背骨」という「恐ろしい絵は、彼女の苦痛をこの上なく印象づける」
著者、堀尾真紀子の前作「フリーダ・カーロ 引き裂かれた自画像」(1992年、中公文庫)に横尾忠則との巻末対談が載っている。
堀尾「向こうで買ってきたフリーダの画集をいろいろ見せるでしょう、・・・で、男の人はね、やっぱり目を背けるというか、『こういうのは出来れば見たくない』って言うわけ」・・・
横尾「芸術というのは本来、吐き出す行為なんだから。自己を探究して、自己の不透明な部分、疑わしい部分、ヤバイ部分、エグイ部分を全部吐き出すという行為が、そもそも芸術行為なんですよ。・・・観念だけで作りあげているのは・・・単に美術ですね」 ・・・
堀尾「誰でも・・・出来れば覗きたくないというか、見たくないというものがあるじゃないですか、それを、白日のもとに曝してしまうという」
横尾「だから気持ち良いんですよ、見る側が。解放されるんです。さらけ出されたことによって、見る側が浄化されるんですよ」
横尾「芸術というのは本来、吐き出す行為なんだから。自己を探究して、自己の不透明な部分、疑わしい部分、ヤバイ部分、エグイ部分を全部吐き出すという行為が、そもそも芸術行為なんですよ。・・・観念だけで作りあげているのは・・・単に美術ですね」 ・・・
堀尾「誰でも・・・出来れば覗きたくないというか、見たくないというものがあるじゃないですか、それを、白日のもとに曝してしまうという」
横尾「だから気持ち良いんですよ、見る側が。解放されるんです。さらけ出されたことによって、見る側が浄化されるんですよ」
フリーダが長年ディエゴと住んだ「青い家」は、今「フリーダ・カーロ美術館」として、観光客が絶えない名所になっている、という。