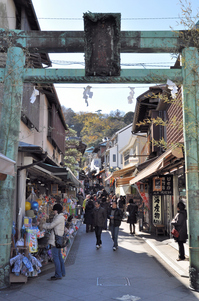世界鉄道博 2016 7月22日
7月16日から9月11日まで、パシフィコ横浜で読売新聞社、BS日テレ主催の「世界鉄道博 2016」が開催されていることを知った。子供たちが夏休みに入ってしまうと混むだろうと思い、7月22日に行ってみた。ネットで検索してみると、レイアウトの規模も大きく、原鉄道模型の未公開の車両も出されているという。
1500円の入場料をお支払いする。入り口の係りの方に「写真を撮っていいですか」と聞いたところ、「OKです」とのこと。
左手のエントランス部の世界の鉄道写真ギャラリーはお馴染の櫻井 寛さんの作品という。左回りに見て歩くが、その左側にZONE-1として、まっすぐに50mにも及ぶ「世界の鉄道模型コレクション」の陳列ケースが並んでいて、、37のケースに約1000両の模型が展示されていた。イギリス、ドイツ、フランす、スイス、イタリア、ベルギーなどのヨーロッパ各国、そして、アメリカ、 日本、オーストラリア、中国の鉄道車両模型が、各ケースにそれぞれ、おおよそ30両ずつ並べられている。原信太郎さんの6000輌にものぼるコレクションの中から、今回はこれまで未公開のHOスケール1150輌が展示されているという。これだけで見に来た甲斐があったと思う。
ZONE-2はZONE-1の右側をヨーロッパ、アメリカ、日本の3つのジオラマに分けた「世界の鉄道物語」というエリアがあった。それぞれのレイアウトをOゲージの鉄道模型が走る。
ZONE-3は「シャングリ・ラ鉄道」の巨大レイアウトだった。実に線路延長650mにもおよぶこのシャングリ・ラ鉄道は、エンドレスを含む28の壮大なレイアウトで、レイアウト上の車輌数はなんと560輌(うち外国型160輌)だそうだ。実際に260輌もの車輌が同時に走るさまは鉄道模型ファンにとってまさに理想郷(シャングリ・ラ)といえるだろう。
この日はG7Xを携えていった。会場は人工光線だけだが、レンズが明るいのでノーフラッシュで、プログラムオートで「シャッター速度速め」に設定しておいたら、1/500、1/1000でシャッターが切れた。しかし、ISOも6400を上限に上がっていくので画像は少々粗くなってしまった。「シャッター速度普通」で試しておけばよかった。
|
1.世界鉄道博 2016 エントランス 10時半、それほど入場客は多くない。子供たちが多いと思っていたが、まだ小学校は夏休みが始まっていないのか、母親に連れてこられた未就学児童がほとんどだった。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.5 1/1000秒 16mm ISO6400) 露出補正 なし |

|
|
2.プロローグ 蒸気機関車、電気機関車、電車の鉄道写真に迎えられて中に入る。世界地図で描かれた路線図もあった。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200) 露出補正 なし |

|
|
3.ZONE-2 世界の鉄道物語 ヨーロッパ ZONE-1のHOゲージ、約1000両の車両模型は後で見ることにして、まず世界の鉄道物語のレイアウトを見ていく。最初はヨーロッパだ。入り口には「イギリスの鉄道のはじまり物語」として、1800年代初期の蒸気機関車の模型が展示されていた。これは実用蒸気機関車の始まりであるロケット号(1829年)だ。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2 1/1000秒 11mm ISO5000) 露出補正 なし |

|
|
4.20世紀の英国の鉄道 レイアウトの手前には、何枚かのパネルがあって興味ある解説がなされている。何といってもイギリスは鉄道発祥の国。しかし、20世紀に入るとドイツやスイスでは電化が進んだが、廉価で良質な石炭が採れ、切通しや橋梁技術など建築土木技術が進展した英国では電化の必要を感じなかったという。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200) 露出補正 なし |

|
|
5.オーストリア、ハンガリー 19世紀にはプロイセン他小国に分かれていたドイツに比べハプスブルグ帝国のオーストリアは欧州屈指の大国だった。ハンガリーは1867年にオーストリアに併合され、オーストリア・ハンガリー帝国となっていた。オーストリアの鉄道では、1998年にユネスコより鉄道施設として最初の世界遺産に指定されたアルプス山脈のゼメリング峠を多数の長いトンネルと、大規模な橋で超えるゼメリング鉄道が有名である。右下の写真は、ヨーロッパ最初のブダペストの地下鉄である。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO4000) 露出補正 なし |

|
|
6.ヨーロッパの鉄道 0ゲージレイアウト ヨーロッパの鉄道の0ゲージレイアウトでは、3本の列車が走行していた。一番外側をTGVが高速で周回する。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.8 1/500秒 22mm ISO6400) 露出補正 なし |

|
|
7.待機するTEEの模型 1957年に登場し国際列車トランスヨーロッパエクスプレス(TEE)に使用された当時の西ドイツ製 DB VT11.5 (BR601) TEE ディーゼルカーが、オリエント急行で有名なプルマンの客車と並んで待機している。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.8 1/320秒 37mm ISO6400) 露出補正 なし |

|
|
8.有名な鉄道車両たちの写真 レイアウトのわきの「Shangri-la Railway since1937」というエンブレムの入ったパネルには、ヨーロッパの鉄道の有名な車両の写真が66枚展示されていた。これから見て歩くアメリカの鉄道、日本の鉄道のわきにもそれぞれ66枚の写真が掲示されている。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO2000) 露出補正 なし |

|
|
9.ヨーロッパの鉄道の機関車たち レイアウトのわきには、有名な蒸気機関車、電気機関車、電車の模型が整列している。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.8 1/320秒 37mm ISO6400) 露出補正 なし |

|
|
10.アメリカの鉄道 ZONE-2、2番目のアメリカの鉄道のレイアウトに移動する。入り口にある「アメリカの鉄道の始まり物語」にある展示ケースには1830年アメリカ最初の蒸気機関車「トム・サム号」と、この写真の1932年のアメリカ最初の実用蒸気機関車「グラス・ホッパー号」が展示されていた。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO4000) 露出補正 なし |

|
|
11.アメリカの鉄道模型編成と子供たち お母さんに伴われた幼い子供たちがアメリカの鉄道模型編成を熱心に見ている。夏休みに入ると小学生たちが大勢見に来ることだろう。子供たちにとって鉄道模型は憧れである。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.8 1/400秒 37mm ISO6400) 露出補正 なし |

|
|
12.アムトラック アメリカの鉄道のレイアウトには、アムトラックの車両があった。アムトラック(Amtrak)は、アメリカ合衆国で1971年に発足した、全米をネットワークする鉄道旅客輸送を運営する公共企業体とのこと。アムトラックの名称は、"America"と"Track"(線路、軌道などの意)の二つの語から合成されたものだそうだ。この電気機関車はAEM-7形といい、1978年から1988年にかけてアメリカ合衆国のアムトラックと通勤鉄道に投入された両運転台、車軸配置B-Bの電気機関車である。主要部品の大半はスウェーデンのASEA (現ABB) が製造しており、最終組立はアメリカのGM-EMDで行われたという。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.8 1/400秒 24mm ISO6400) 露出補正 なし |

|
|
13.日本の鉄道 アメリカの鉄道の次には日本の鉄道のレイアウトがあった。「日本の鉄道の始まり物語」には江戸時代の1853年、日本人が初めて作った鍋島藩の蒸気機関車の模型がった。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO5000) 露出補正 なし |

|
|
14.京成1600 開運号 レイアウトには珍しい車両の模型があった。京成電鉄の1600形電車は1953年(昭和28年)に特急開運号の専用車両として作られた車両だった。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.5 1/500秒 17mm ISO6400) 露出補正 なし |

|
|
15.旧国鉄の蒸気機関車たち 流線型のC55を中心に旧国鉄の蒸気機関車のOゲージ模型も並べられている。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.8 200秒 37mm ISO6400) 露出補正 なし |

|
|
16.シャングリ・ラ鉄道 ZONE-3はシャングリ・ら鉄道の巨大なHOゲージレイアウトだ。原信太郎氏(1919-2014)が1937年に自宅で創設した鉄道模型の理想郷「シャングリ・ラ鉄道」に由来しており、「鉄道は世界をつなぐ 」の理念の下、国内外の車両の鉄道模型が縦横無尽に走行する。「サンライズ・エクスプレス」のHOゲージ編成が走行中だった。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1000秒 9mm ISO3200) 露出補正 なし |

|
|
17.シャングリ・ラ鉄道 メンテナンス シャングリ・ラ鉄道のレイアウトは広大であるが、ジオラマにはなっていない。その敷き詰められた線路のわきで走行する列車のメンテナンスをされているご高齢の方がおられた。鉄道模型がお好きな方なのだろうなと思う。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.5 1000秒 15mm ISO6400) 露出補正 なし |

|
|
18.シャングリ・ラ鉄道の車両 シャングリ・ラ鉄道では560輌(うち外国型160輌)のHOゲージ車両模型が投入されている。実際に260輌もの車輌を同時に走らせることがあるようだが、鉄道模型ファンにとってはワクワクすることだと思う。手前にあるのはS-BAHNの車両。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.8 400秒 37mm ISO6400) 露出補正 なし |

|
|
19.横浜および横浜近郊の鉄道会社 シャングリ・ラ鉄道のわきの壁面にはJR東日本や大手私鉄の京浜急行をはじめ、湘南モノレールなどの横浜および横浜近郊の鉄道会社のブースが設けられていた。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1000秒 9mm ISO3200) 露出補正 なし |

|
|
20.鉄道ワンダー・ランド シャングリ・ラ鉄道の広大なレイアウトの向こうにあるのはZONE-4の鉄道ワンダー・ランドだ。子供たちが楽しめるようになっている。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.8 320秒 37mm ISO6400) 露出補正 なし |

|
|
21.きかんしゃトーマス きかんしゃトーマスは1984年からイギリスで放送が始まった1番ゲージの鉄道模型を使用して撮影される人形劇、現在はコンピュータを使用して制作されるCGアニメーションとして放送されている幼児向けテレビ番組である。日本ではフジテレビで1990年から2007年まで放映された。ここにはトーマスを中心にジェームスとステップニーの3台の機関車があった。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1000秒 9mm ISO2500) 露出補正 なし |

|
|
22.最後に見たZONE-1の1000両の鉄道模型 さて、ZONE-2からZONE-4まで見終わって、いったん最初の「世界の鉄道プロローグ」まで戻ってきた。最後にZONE-1の「世界の鉄道模型コレクション」を見ることにする。会場の左サイドにまっすぐに陳列ケースが連なる。一つ一つの車両の説明はない。イギリスから始まって中国まで約1000両のHOゲージの鉄道模型が並べられていた。これはイタリアのケース。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2 1000秒 11mm ISO400) 露出補正 なし |

|
|
23.イタリアの鉄道模型 これはディーゼル機関車だろうか。とてもユニークな形をしている。D341形か。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1000秒 9mm ISO500) 露出補正 なし |

|
|
24.アメリカの蒸気機関車 この模型はニューヨーク・セントラル鉄道の5405蒸気機関車。日本のC62と同じ形式のハドソン型蒸気機関車である。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1000秒 9mm ISO800) 露出補正 なし |

|
|
25.中国の電気機関車 「世界の鉄道模型コレクション」の最後の1台がこの模型だった。中国の鉄道模型はこの1台しかなかった。形式番号6Y209が読み取れる。Wikipediaによれば、この6Y2型はフランスのアルストムが製造した、中国の輸入電機で初の大型電気機関車である。1961年、中国で初の電化路線の宝鶏 - 鳳州間が完成、導入予定の中国初の国産電気機関車6Y1型が性能不足の為、1960年にフランスのアルストムから総計25両の本形式を輸入したとある。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1000秒 9mm ISO400) 露出補正 なし |

|