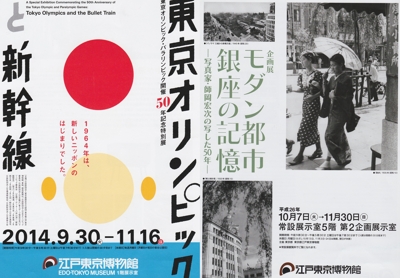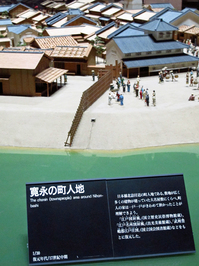人形町・水天宮・門前仲町 5月16日
あれは東日本大震災の年だったと思う。古希を迎えた小学校の同級生で、クラス会を行った折に、これからは半年に一度は会う機会を作ろうかということにして、もう、5年が過ぎた。前回集まった時に、次回は人形町の「玉ひで」さんの親子丼を食べたいとの意見が出た。私も以前に2~3回並んで順番を待って「玉ひで」の親子丼を食べたことがある。しかし、まとまって座って、ちょっとゆっくりしたいとなると、並んで待って、食べ終わったらすぐ出るというのでは落ち着かない。「親子昼膳」を予約して席を確保することにした。
いつものクラス会は8名~10名くらい集まるのだが、今回は参加者が6人と少なかった。しかもひとりが日にちを勘違いしてドタキャンになった。幸いキャンセル料は勘弁していただいたが・・・
食後の腹ごなし散策のこともあるので、私は少し早めに行って、人形町界隈を歩いてみることにした。横浜から人形町へは京浜急行、都営地下鉄浅草線直通で乗り換えなしで行けた。
人形町駅で下車、まず、久松町の方へ歩いてみる。そこから浜町へ。甘酒横丁を通って、人形町へ戻ってきて、クラスメートと落ち合った。
「玉ひで」さんでは、江戸の古地図の屏風が置かれた落ち着いた椅子席に案内された。親子丼は旨かった。
「玉ひで」を出て、安産はもう関係ないが、まず水天宮へお参りした。すっかり新しくなっている。
男3人、女2人の一行は、水天宮から地下鉄半蔵門線に乗って清澄白河で都営大江戸線に乗り換え門前仲町へ。深川不動堂、富岡八幡宮にお参りし、喫茶店でしばし話に花を咲かせた後、次回の約束をして解散となった。
|
1.明治座 人形町から久松町へ出て、久松町の交差点を右に曲がり、清州通り進むと、こののぼりが見えてきた。明治座だ。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影( f4 1/320秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
2.新しくなった明治座 明治座がこのビルに入ったのは1993年だ。wikipediaによると、明治時代からの長い歴史を持つ「日本橋明治座」は、「銀座歌舞伎座」「新橋演舞場」「お堀端帝劇」などとともに、東京を代表する劇場として親しまれてきた。1945年(昭和20年)3月10日の東京大空襲で焼失した明治座は、その残骸をむき出しのまま放置されていたが、地元有志の間で明治座復興の気運が盛り上がり、再建され1950年(昭和25年)11月30日に開場に漕ぎ着けた。1993年には、再開発で建て替えた賃貸オフィスビルの浜町センタービル低層階を占める形となっている。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影( f4 1/400秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
3.玉ひで 明治座から甘酒横丁を人形町方面に戻る。5月21日、TV番組の「路線バスの旅」で徳光和夫さん、伍代夏子さん、田中律子さんが、この通りを歩いていた。人形町通りを渡って少し行くと、この日親子丼を食べる「玉ひで」さんだ。予約をしておいたので、落ち着いた部屋の椅子席で「親子昼膳」を食べながらのひと時を過ごした。旨かった。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影( f3.1 1/800秒 4mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
4.水天宮 「玉ひで」を出て、まず、水天宮にお参りする。水天宮も新しくなっている。wikipediaによれば、江戸鎮座200年記念事業として社殿の建て替えを行った。それに伴い、平成25年(2013年)3月1日から平成28年(2016年)4月7日までの間は、日本橋浜町の明治座そばに仮宮(位置)が設けられていた。これは少なくとも、昭和40年代初期に嵩(かさ)上げ工事をして二階建てとなって以来、ほぼ半世紀ぶりの遷座である。平成28年4月8日より新社殿への参拝者の受け入れを開始したとある。このコンクリートの階段がいわば参道なのだろう。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影( f3.5 1/80秒 6mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
5.水天宮新社殿 白木を基調とした神社建築様式を取り入れられている。また代々受け継がれている伝統文化の錺金具や彫刻等も施されている。免震構造など最新技術を用い、古きよきものと新しきものを取り入れた、時代に即した社殿という。安産、子授けはもはや関係ないがお参りをした。ここが、福岡勤務時代に訪れたことがある福岡県久留米市の久留米水天宮の分社とは知らなかった。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.7 1/400秒 7mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
6.水天宮 子宝犬 周囲を取り巻く十二支のうち自分の干支を撫でると安産、子授け、無事成長など様々なご利益があるのだそうだ。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.7 1/320秒 7mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
7.深川不動堂入り口 水天宮前から地下鉄半蔵門線(東京メトロ)に一駅乗り、清澄白河で都営大江戸線に乗り換え、また一駅乗って門前仲町で下車した。永代通りの朱塗りの門を入ると深川不動堂の参道だ。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.1 1/640秒 4mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
8.深川不動堂 旧本堂とわらじ願掛け 深川不動堂は、真言宗智山派の寺院であり、千葉県成田市にある成田山新勝寺の東京別院である。正面に見えるのは旧本堂で、前本堂が東京大空襲で焼失した後、千葉県本埜村(現・印西市)の龍腹寺の堂(文久3年・1863年建立)を移築して本堂としたもので、昭和25年(1950年)に移築が完了、翌年に落慶法要が営まれている。旧本堂の西側(写真では左側)にある外壁に梵字(不動明王真言)を散りばめてある建物が現在の本堂で、開創310年を期に平成23年(2011年)に完成したそうだ。境内に足を踏み入れて目立つのは巨大なわらじだ。これには願かけの絵馬やわらじが無数にぶら下げられていた。この巨大なわらじは本堂に登る石段の両側にあり大変目立つ。靴を脱いで旧本堂に上がって、およそ10,000体のクリスタル五輪塔が祀られている「祈りの廻廊」、4階にある天井画「大日如来蓮池図」、そして本堂で行われていた護摩行を見学した。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.7 1/500秒 7mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
9.深川開運出世稲荷 境内に成田山開運出世稲荷の分霊である稲荷社があった。「荼枳尼天尊」の扁額がかかっている。よく判らないが、狐が玉のようなものを咥えている。反対側の狐も何かを咥えている。狛犬と同様に社殿に向かって右(上座)が口を開いた「阿(あ)」であり、左(下座)が口を閉じた「吽(うん)」と言われるがここのは左右同じように見える。稲荷神社の狐は玉のほかにも鍵や鎌や稲穂を咥えた狐もいて、いくつかのバリエーションがあるようだ。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.1 1/640秒 4mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
10.富岡八幡宮 分社 深川不動堂を出て左へ行き、富岡八幡宮の鳥居をくぐって境内に入る。その左手にひっそりとこの分社があった。左から、富士浅間社、金刀比羅社、大黒社、恵比寿社、鹿島神社、大島神社とある。正面から入るとここは境内の一番奥になる。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/160秒 5mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
11.富岡八幡宮 本殿 本殿は改修中だった。本年例大祭までを完成目標として、外壁等の塗り替えを中心に、本殿、南参道鳥居、西参道鳥居の修繕工事が行われていた。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.4 1/250秒 12mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
12.日本一の御神輿 一の宮神輿と二の宮神輿があるが、この一の宮神輿の方が大きい。説明板などによると、富岡八幡宮にはもともと、江戸、元禄時代に深川に屋敷があった紀伊国屋文左衛門より、三社託宣に因み、八幡造り、神明造り、春日造りの三基三様の神輿が奉納され、みこし深川と言われてきたが、大正12年の関東大震災で惜しくもそのすべてを焼失した。長い年月、宮神輿がなかったが平成になり、昔に優るとも劣らない豪華なお御神輿が復活した。日本最大の神輿と言われている高さ4.4メートル重さ4.5トン、随所に純金・宝石が散りばめられた絢爛豪華な一の宮神輿が平成3年(1991年)に奉納された。神輿の最上部の鳳凰や中段の狛犬のダイヤモンドの目は光り輝いており、非常に豪華な作りになっている。一の宮神輿は非常に大きすぎて担ぐ事が出来ないということで、1997年(平成9年)に、この一の宮神輿の右側に置かれている二の宮御輿が作られ御本社祭りの際担がれる様になった。こちらは一回り小さいが、それでも高さ3.3メートル重量2トンもある。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.1 1/60秒 4mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
13.木場の木遣りの碑 富岡八幡宮の正面まで来た。大関力士碑があり、横綱力士碑は本殿の横にあるとあったので、先にそちらを見に行こうと東参道へ入るとこの木遣りの碑(角乗り碑)があった。「木場の木遣り」の発祥は古く、現存の文献によれば、既に慶長初期の昔に行れている。当時、幕府のお船手の指図で、伊勢神宮の改築用材を五十鈴川より木遣りの掛け声で水揚げをした、とある。元来、神社仏閣の鳥居や大柄な用材を納める場合には木場木遣り特有の「納め木遣り」が用いられ、保存会により今日に伝えられている。元禄の始めには、武家屋敷の並ぶ両国の七つ谷の倉の間部河岸という所で3代将軍家光公に筏の小流し(さながし、筏組)、角乗り、木遣りをご覧に入れ、以後年中行事となった。この時、川並みという言葉が発祥したと伝えられる。 江戸の昔より正月2日から7日に掛け木遣りにて初曳きし、材木屋さんに売り捌くのを年中行事としていた。これはブログ「東京都江東区の歴史」より引用させていただいた。また、「東京ぐるり」というブログを見ると、木材の町「木場」は、江戸時代より昭和50年「新木場」に移転するまで約270年間木材産業の町として栄えた。江戸材木置場は、寛永18年(1641年)、明暦3年(1657年)の大火後、永代島に集中移転し木場と称した。元禄14年(1701年)現在の木場に移転以来270年間、木場は繁栄を続けた。昭和51年夏までに大半の材木業者が夢の島の新木場に移転したとあった。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.1 1/60秒 4mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
14.七渡神社 弁天池の真ん中の道の向こうに七渡神社がある。立てられれていた説明板には、「七渡神社は八幡宮御創建以前よりお祀りされ、八幡様の地主神として七渡弁天さまと尊ばれて参りました。あわせてお祀りされる粟島神社は女性の守り神として2月8日に献針祭(針供養)が行われます。」と記されていた。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/80秒 5mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
15.横綱力士碑 目当ての「横綱力士碑」は改修中の本殿の東側にあった。富岡八幡宮のホームページによると、富岡八幡宮は江戸勧進相撲発祥の地として有名である。江戸時代の相撲興業は京・大阪から始まるが、 トラブルが多くしばしば禁令が出た。その後禁令が緩み、貞享元年(1684)幕府より春と秋の2場所の勧進相撲が許された。その地こそがこの富岡八幡宮の境内だった。以降、約100年間にわたって本場所が境内にて行われ、その間に定期興行制や番付制が確立されたそうだ。そののち本場所は、本所回向院に移っていくが、その基礎は富岡八幡宮において築かれ、現在の大相撲へと繋がっている。明治33年、第12代横綱陣幕久五郎を発起人に歴代横綱を顕彰する碑がここに建立された。そして新横綱誕生時には相撲協会立会いのもと刻名式が行われ、新横綱の土俵入りが奉納される。また両側には伊藤博文、山県有朋、大隈重信といった賛同者の名が刻まれており、広く各界から協賛を得て建立されたことを物語っている。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/80秒 5mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
16.大関力士碑 こちらは富岡八幡宮の正面、大鳥居をくぐってすぐ右手に歴代大関を顕彰するために建立された 「大関力士碑」がある。この碑は明治の頃に、9代目市川団十郎と5代目尾上菊五郎により寄進されていた2基の仙台石を活用し、初代大関雪見山から2014年3月に引退した琴欧州まで歴代大関114名の四股名が彫り込まれている。(大関に在った力士が引退した時にその四股名が彫り込まれるとのこと)
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.1 1/80秒 4mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
17.スカイツリー 富岡八幡宮のお参りの後、喫茶店でしばし昔話を楽しんだ後、クラス会は解散になった。みんなは門前仲町から地下鉄に乗ったが、私は人形町まで歩くことにした。永代通りを永代橋に向け歩く。途中、福島橋から右手に御船橋、緑橋、そしてその向こうにスカイツリーが見えた。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影( f5.6 1/125秒 34mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
18.永代橋 墨田川にかかる大きな永代橋を渡る。永代橋は、元禄年間に「深川の大渡し」に代わって架けられ、佐賀町付近(現在の佐賀一丁目付近)が昔、永代島と呼ばれていたため、永代橋と名付けらた。現在の橋は、1926年に架けられたもの。1897年に、道路橋としては日本で初めて鉄が使用されたが、床が木製だったため関東大震災で焼損し、震災復興橋として現在の姿となったそうだ。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/125秒 34mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
19.佃島タワー・マンション群 永代橋の左側(南側)には、墨田川の向こう、佃島エリアの高層マンション群が聳える。高層マンションは8棟あり、大川端リバーシティ21と呼ばれている。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5 1/125秒 22mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
20.人形町からくり櫓 永代通りを新川1丁目で右に曲がり、湊橋を渡って、東京シティ・エア・ターミナルに出た。そこを左に水天宮の方へ進む。そして人形町通りを人形町交差点へと進む。その人形町通りに「人形町からくり櫓」があった。時間になると人形たちが生き生きと動き出し、道行く人々の目を釘付けにするという。こちらは「江戸落語からくり櫓」で、道の反対側には「江戸火消しからくり櫓」があった。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.7 1/125秒 7mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
|
21.鉄造菩薩頭 この寺は大観音寺という。鎌倉の新清水寺にあった鋳鉄製の観音像が鎌倉時代に火災に遭い、後に頭部のみが掘り出され、その後鶴岡八幡宮に安置されていたが、神仏分離令により現在の大観音寺に遷座となったそうだ。それが明治9年のことで、安置されているここ大観音寺は明治13年に建立された。鉄造菩薩頭は関東に現存する中世に造立されたものの中でも特に優れていることから、昭和47年に東京都有形文化財に指定された、といったことが中央区教育委員会の立て札に記されていた。
Panasonic DMC SZ-10 f3.1-6.3 4.3mm-51.6mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.7 1/30秒 7mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
: