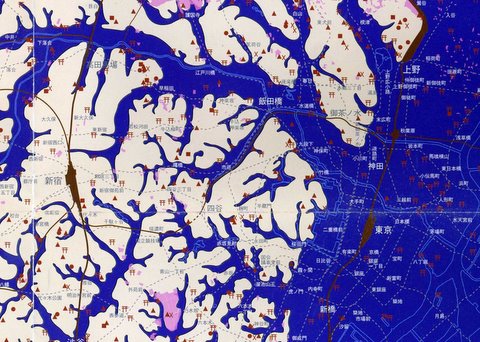読書日記「昭和三十年代 演習」(関川夏央著、岩波書店刊)
著者と若い編集者が、昭和30年代によく読まれた本や映画などをテキストに勉強会を開く。著者をリーダーに、若い世代が現在につながるこの時代の意識を知ろうという狙い。だから「演習」というわけらしい。
この時代を中学生から大学生までを過ごした前期高齢者としては「演習」に出て来る素材のほとんどがなつかしい。かつ「ああ!あの時代を無為にすごしてしまったなあ」という感覚、感情がなんとなくツーンと胸を衝いた。
「BOOK」データベースには、こうある。
昭和三十年代とは、どのような時代だったのだろう。明るく輝き、誰もが希望に胸をふくらませていた時代だったのだろうか。貧乏くさくて、可憐で、恨みがましい―そんな複雑でおもしろい当時の実相を、回顧とは異なる、具体的な作品と事象の読み解きを通して浮き彫りにする。歴史はどのようにつくられ、伝えられてゆくのか。歴史的誤解と時代の誤読を批判的に検討する。
松本清張の初期短編 「張り込み」を映画化した昭和33年の同名映画の冒頭10分間は、真夏の夜行列車の車中の描写だった。本筋とは深い関係はないのに「監督の野村芳太郎が描きかったのは、実は日本の夏の蒸し暑さではなかったか」と、著者は書く。
暑い。ものすごく混雑している。汗でべたべたする。誰もが扇子をあわただしく使います。なんとか座席を確保できた人は、それが男性なら、ほぼ間違いなくズボンと上着を脱ぎ、ワイシャツまで脱いでステテコの下着姿になります。・・・
それほど、当時の旅行は一種の力仕事でした。
それほど、当時の旅行は一種の力仕事でした。
中学2年の頃だっただろうか。ある団体に参加を許されて、東京に国会議事堂見学や靖国神社参拝の夜行列車に乗ったことがある。トンネルに入る度に、蒸気機関車の煙が入らないよう、あわてて窓を閉めた。ウトウトして目覚めた明けがた、引率者がくれた初めての冷凍ミカンの味がいまだに忘れられない。
昭和30年代は「いちおう戦後復興をとげた敗戦国日本が痛切に『世界復帰』を願った時代」でもあった。
南極観測の世界会議に日本は無理やりという感じで出席した。「日本はまだ国際社会復帰の資格はない」という冷たい雰囲気のなかで、なんとか参加が認められた。この時、割り当てられたプリンス・ハラルド海岸は「実は接岸不能とされた地図空白地帯でした」
外国から借りるつもりだった観測船は実現せず、結局、海上保安庁の老補給船 「宗谷」が使われた。初の越冬隊を残し帰国の途についた「宗谷」は堅い氷海に閉じ込められ、ソ連の砕氷船「オビ」に救援された。
果敢なのに貧弱な装備しか持たない「宗谷」と越冬隊の姿は、戦後日本の姿そのもののようでした。子どもたちは、「不当に」世界から置き去られている日本と、氷海に閉じ込められた「宗谷」を自分の一部とみなし、その遭難と脱出のニュースを、文字どおり手に汗握って聞いたのです。
「普通の日本人が、外国を一挙に実感する『事件』が昭和37年8月に起きた」。 堀江謙一青年のヨットによる単独太平洋横断だ。
サンフランシスコに着いた堀江青年は、ぼさぼさに髪が伸びた頭に工員帽をかぶり、素足にサンダルでガニ股、はにかんだ青年の写真は「まさに絵にかいたようなプロレタリアの姿」だった。
堀江謙一の冒険は、一気にアメリカを日本に近づけました。それまで、弱い円と乏しい外貨のせいで事実上の鎖国を強いられ、政務か商用、あるいはフルブライト留学生くらいしか行けなかったアメリカを、いわば「プロレタリアでも行けるアメリカ」にかえたのでした。・・・堀江青年の冒険は、敗戦国からの脱皮という意味で大きなできごとでした。
内モンゴルの研究をしていた梅棹忠夫は「中央公論」の昭和32年2月号に載せた論文 「文明の生態史観序説」で「日本はアジアではない」「アジアという実体は存在しない」という考えを初めて明らかにした。
日本はユーラシア大陸東辺の海中にあったからこそ、遊牧民の破壊的エネルギーからまぬがれた。結果、小ぶりな閉鎖系とはいえ独自文明の名に値するものを生み出し得た。そのような環境条件は、ユーラシア大陸の反対側、西方の海中にある英国とおなじだったーーー・・・
「アジアでなくてもよい」とは、日本が欧米の仲間だというのではありません。日本は「海のアジア」であって「大陸のアジア」ではない、せっかく海の存在によって大陸と距離をおくことができたのだから、「大陸アジア」と無理に親和する必要はないというのです。
「アジアでなくてもよい」とは、日本が欧米の仲間だというのではありません。日本は「海のアジア」であって「大陸のアジア」ではない、せっかく海の存在によって大陸と距離をおくことができたのだから、「大陸アジア」と無理に親和する必要はないというのです。
さきにこのブログでふれた鼎談集 「時代の風音」で司馬遼太郎が「日本は、アジアの国々とは別の国」と語っていたのを思い出した。
梅棹忠夫と司馬遼太郎は、モンゴル研究を通じて長年の友人だったそうだから、両氏の意見が似ているのも当然のことだったのだ。
しかし「大陸・中国」が最近、露骨に海の覇権を握ろうとする動きを強めるなかで、日本は「海のアジア」とノホホンとし続けられるのか。
世界の異端児・北朝鮮が「一部とはいえ『世界の楽園』と賞讃」されたのも、昭和30年代。昭和34年には、在日コリアンの北朝鮮への「帰国運動」も始まった。
父親を戦争でなくし母一人の手で育てられ、ボロ家に住み続けた昭和30年代。どこから回ってきたのか、北朝鮮の華やかなカラー雑誌を見ながら「北朝鮮に行ってみようか」と一時は真剣に思ったことを、戦慄を持って思いだす。
昭和39年秋に 東京オリンピックが開催された。
昭和三十八年夏から秋、(オリンピックの)工事で穴だらけになった東京の姿は、まだ若かった篠田正浩が石原慎太郎の小説を映画化した松竹作品 『乾いた花』に記録されています。
建設途中で一部のみ開通した首都高速道路を加賀まりこがスポーツカーを走らせます。助手席にいるのは 池辺良です。・・・
このくだりは、石原慎太郎が・・・第二京阪国道でスポーツカーと自然に競争になり、あとで相手は 力道山だったと気付いた、というエピソードから発想されています。
当時、東京のど真ん中・四谷にあった大学の4回生だった。貧乏学生にチケットを買う余裕などない。開会式の日、自衛隊の 「ブルーインパルス」が空中に描いた五輪のマークを見上げたのが、唯一のオリンピック体験だった。
昭和39年10月24日、国立競技場の閉会式の「雑感」を読売新聞の遊軍記者、 本田靖春は、社に電話送稿した。
白い顔も、黒い顔も、黄色い顔も・・・若ものたちはしっかりスクラムを組んで一つになり、喜びのエールを観客とかわしながら、ロイヤル・ボックスの前を、"エイ、エイ"とばかりに押し通った。
その前を行く日本チームの 福井誠旗手は、あっという間に一団にのみこまれ、次の瞬間、かれのからだは若ものたちの肩の上にあった。かれがささげる日の丸は、そのミコシの上で、右へ、左へ、大きく揺れた。
その前を行く日本チームの 福井誠旗手は、あっという間に一団にのみこまれ、次の瞬間、かれのからだは若ものたちの肩の上にあった。かれがささげる日の丸は、そのミコシの上で、右へ、左へ、大きく揺れた。
2020年に東京オリンピックが、56年ぶりに開催されることが決まった。
その招致プレゼンテーションで、安倍首相は「福島原発の汚染水は、完全のコントロールされており、日本のどこもが安全だ」と大見得を切った。しかし、汚染水対策解決の見通しなどまったく立っていないというのが真実だ。首相は、世界に向けて事実とは異なる発言で、2回目のオリンピックを勝ち取った。
「世界への復帰」を熱望した昭和30年代という時代を経て、 G7(先進国首脳会議)のメンバーになるほどの経済成長をとげた日本は、どんなポジションで2020年を迎えるのだろうか。
Amazonの「カスタマーレビュー」に、この著書が取り上げた本などの抜粋が載っていた。
- 西岸良平『三丁目の夕日 夕焼けの詩』
- 松本清張『日本の黒い霧』『点と線』『西郷札』『或る「小倉日記」伝』『ゼロの焦点』 『けものみち』『砂の器』『眼の壁』
- 石原慎太郎『太陽の季節』
- 森鴎外『舞姫』『阿部一族』『渋江抽斎』
- 三島由紀夫『午後の曳航』『豊饒の海」『鏡子の家』『宴のあと』『憂国』『仮面の告白』 『金閣寺』『鹿鳴館』『愛の渇き』『青の時代』
- 山本嘉次郎監督『綴方教室』
- 成瀬巳喜男監督『浮雲』
- 井筒和幸監督『パッチギ!』
- 芥川龍之介『舞踏会』
- 山田風太郎『エドの舞踏会』
- フランソワーズ・サガン『悲しみよこんにちは』
- 堀江謙一『太平洋ひとりぼっち』
- 木下恵介監督『喜びも悲しみも幾年月』
- 大庭秀雄監督『君の名は』
- 安部公房『砂の女』
- 寺尾五郎『38度線の北』
- 金元祚『凍土の共和国―北朝鮮幻滅紀行 』
- 安本末子『にあんちゃん』
- 山田洋次監督『男はつらいよ』
- 浦山桐郎監督『キュ-ポラのある街』
- 石坂洋次郎『陽のあたる坂道』『若い人』『青い山脈』
- 大江健三郎『ヒロシマ・ノート』
- 大島みち子・河野実『愛と死をみつめて―ある純愛の記録』
- 高野悦子『二十歳の原点』
- 本田靖春『不当逮捕』
- 市川崑監督『ビルマの竪琴』
- 川島雄三監督『幕末太陽傳』
- 田中絹代監督『乳房よ永遠なれ』
- 中平康監督『狂った果実』
- 今井昌平監督『豚と軍艦』
- 舛田利雄監督『赤いハンカチ』
- 江崎実生監督『夜霧よ今夜もありがとう』
- マイケル・カーティス監督『カサブランカ』
- キャロル・リード監督『第三の男』
- ジュリアン・デュヴィヴィエ監督『望郷』
- 早坂暁脚本『夢千代日記』
- 小松左京『日本沈没』
ああ昭和、30年代は遠くなりにけり!