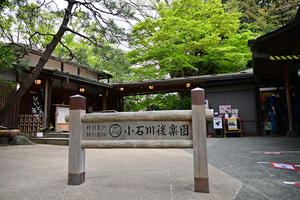ある旅行会社が企画した「江戸城歴史ウォーキング」というコースに参加した。
JR東京駅丸の内中央口(9:50)集合・・・和田倉門左折・・・皇居外苑・・馬場咲門右折・・・正門石橋・・・二重橋・・・坂下門・・・桔梗門、桜田二重櫓・・・大手門【江戸城の正門】・・・ 大手三の門【同心番所】・・・百人番所・・・中ノ門跡【江戸城内最大級の巨石】・・・大番所・・・中雀門【本丸に通じる最後の門】 ・・・本丸御殿跡【大奥があった】・・・展望台・・・富士見櫓【現存する唯一の三重櫓】・・・松之大廊下跡【元禄赤穂事件発生の場所】・・・富士見多聞【長屋造りの武器庫】・・・石室・・・天守台【天守閣跡】・・・汐見坂(遠望)・・・北桔橋門【東御苑の出入口】・・・北の丸公園・・・田安門・・・そこから再び北の丸公園に戻って[なだ万]謹製のお弁当が配られた。
江戸城のことは普段いろいろ見聞きすることはあるものの実はその歴史の多くは理解していない。 ガイドの方が付いてくれて説明をしてくださった。なかなか解り易い説明でとても有意義な半日だった。
1.東京駅北口ドーム
東京駅には9時20分ごろに着いた。北口改札を出ると朝の光が差し込んだドームの天井があった。
Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/160秒 6mm ISO800 ) 露出補正 なし
|

|
2.丸ビル
集合場所は東京駅の「丸の内中央口を出たところ」だった。集合時間になると点呼がとられ、ガイドさんが紹介された。32名が参加している。まず、ガイドさんから、丸ビルは32万石の岡山藩池田家の上屋敷があったところだと説明された。
Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f5 1/1250秒 6mm ISO800 ) 露出補正 なし
|

|
3.旧国鉄本社 現在は丸の内オアゾ
このビルは旧国鉄本社のあったところ。熊本細川家54万石の上屋敷のあったところで、このあたりにあった江戸藩邸として最も大きい大名だったという。ちなみに前田家の江戸藩邸は東大本郷キャンパスにある。東大赤門は旧加賀藩主前田家上屋敷の御守殿門であり、1827年に第12代藩主前田斉泰が第11代将軍徳川家斉の第21女、溶姫を迎える際に造られたそうだ。国の重要文化財とのこと。東京国際フォーラムのあるところは坂本龍馬の藩である土佐藩山内家の江戸藩邸があったそうだ。
Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f8 1/12500秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし
|

|
4.和田倉門交差点
一行32名がぞろぞろと行幸通りを真っ直ぐに進んで、和田倉門の交差点に出る。和田倉門はかって江戸城の守衛のために築かれた内郭門の一つだそうだ。橋を渡ると皇居外苑側には枡形石垣があり、橋と一体で門を構成している。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/500秒 38mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
5.コサギ
和田倉橋を渡るとコサギがいた。和田倉橋の左側は馬場先濠。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/800秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
6.和田倉濠と石垣
江戸城の石垣の構造は打込み接ぎ(はぎ)と切込み接ぎとがある。打込み接ぎは表面に出る石の角や面をたたき、平たくし石同士の接合面に隙間を減らして積み上げる方法である。関ヶ原の戦い以後、この手法が盛んに用いられた。野面積みより高く、急な勾配が可能になる。一方、切込み接ぎは方形に整形した石材を密着させ、積み上げる方法である。慶長5年(1600年)以降、隅石の加工から徐々に平石にまでわたるようになり、江戸時代初期(元和期)以降に多用されるようになったそうだ。石材同士が密着しているので排水できないため排水口が設けられる。江戸城の石垣は切込み接ぎが多く用いられているが、この積み方は時間を要する。ここは打込み接ぎだ。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/400秒 32mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
7.切込み接ぎの石垣
こちらは切込み接ぎの石垣だ。隙間がなく形を整えられた石が積まれている。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 32mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
8.皇居前広場
皇居前広場は芝生と黒松が植わっている広場で、珍しいとガイドさんは言う。皇紀2600年を記念して今のような姿になったそうだ。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1000秒 75mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
9.丸の内のビル街
皇居前広場からは丸の内や日比谷のビル街が眺められる。この写真の後ろ側は内堀通りが縦貫する。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/500秒 26mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
10.二重橋と伏見櫓
私は二重橋を見たことがない。写真などで見るめがねのような橋が二重橋とばかり思っていたが、本当の二重橋はその奥にある橋だという。その向こうに見えるのは伏見櫓で江戸城築城の第二期(三代将軍家光の時)の寛永五年(1628年)に京都伏見城から移築したものと伝えられている。それ以来燃えたことがないとガイドさんが話してくれた。東日本大震災の時白壁をつくりかえた。別名で「月見櫓」とも呼ばれており、皇居で最も美しい櫓と言われ櫓の高さ約13.4メートルあるそうだ。もっと先の正面石橋の近くまで行けるようなので行ってみたかったがガイドさんは右へ曲がってしまった。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1000秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
11.ほんとの二重橋
これが二重橋と思っていた石の橋の向こう側に鉄の橋が見える。堀が大変深く、江戸時代には補強のため橋桁を上下二重に組んで橋の上に橋を作っていたので二重橋と呼ばれていたそうだ。明治になって鉄製になったので「正門鉄橋」が正式名称になっているという。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1640秒 66mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
12.正門石橋
私はこのメガネのような橋を二重橋とばかり思っていた。一般的にはそうだと思う。しかし、これは「めがね橋」でも、「二重橋」でもなく正式名称を「正門石橋」というそうだ。しかし、今朝配られた「江戸城歴史ウォーキング散策マップ」には二重橋となっている。手前の「正門石橋」と奥の「正門鉄橋」を合わせて二重橋が通称になっていると記されていた。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/640秒 40mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
13.正門石橋と正門鉄橋
この位置から見ると正門石橋と正門鉄橋が良くわかる。もっと先まで行けるようなので行ってみたかったが。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 45mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
14.坂下門
内堀の前を歩いて坂下門に出た。手前の橋は皇居外苑から皇居(旧江戸城西の丸)に通じる土橋で坂下門橋という。門内の近くに宮内庁がある。坂下門は江戸城西の丸造営直後に造られたと伝えられていて西の丸大奥に近く、西の丸の通用門として利用されていたが、今は宮内庁の出入口となっている。文久2年(1862)1月、老中安藤対馬守がこの門外で水戸浪士に襲われたのが「坂下門外の変」だ。この中には入れない。正月・天皇誕生日の一般参賀の際の出口のひとつとして指定されており、一般人が通れるのはこの機会以外にはないそうだ。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 100mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
15.坂下門と宮内庁
坂下門を左手に見ながら桔梗門(内桜田門)へ歩く。左手は蛤濠だ。宮内庁の建物が見える。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/800秒 52mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
16.桔梗門(内桜田門)
三の丸への出入り口だそうだ。かってこの門の瓦などに太田道灌の家紋である桔梗の紋が施されていたことから桔梗門と呼ばれる。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 42mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
17.桜田二重櫓(巽櫓)と内桜田門 その奥に富士見櫓
桜田二重櫓(巽櫓)は江戸城に残る唯一の隅櫓だそうだ。明暦の大火のあと1659年以来焼けていない。本丸から見て巽の方角にあるので巽櫓桜田二重櫓(巽櫓)ともいう。関東大震災で損壊したのちに解体して復元されている。歩いてきた内桜田門の奥に三重櫓である富士見櫓が見えた。天守閣が明暦3年(1657年)の大火で焼失した後は復旧されなかったので、富士見櫓が天守閣に代用されたと伝えられている。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 27mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
18.桜田二重櫓(巽櫓)
石落としが備わっており、実戦的な櫓としてつくられたという。直角に曲がる桔梗濠には藻(アオコ)が生えている。お堀の水はどう流れているのだろうか?ネットで検索してみる。江戸時代から明治時代の中頃までは、お濠は江戸の六上水の一つである「玉川上水」と接続しており、玉川上水は最も水位の高い半蔵濠、千鳥ヶ淵に流れ込んで、各濠の水門を順繰りに下りながら、最も低位の日比谷濠から江戸湾(東京湾)に流れ出るという「きれいな水の循環」が作られていたという。ところが時代は過ぎ、1965年(昭和40年)、それまでお濠に流れ込んできていた玉川上水が完全に廃止され、きれいな水の供給は途切れ、お濠の水はほとんど雨水に頼らざるを得なくなった。水たまりになったのだ。それに加えて、外苑濠には長年にわたり周囲からの落葉等が流れ込んでくる。このような状況を受け、濠を管理する環境省では、平成7年から濠水浄化施設の運用を行うなどの対策を行ってはきた。平成25年4月から運転を開始している「新濠水浄化施設」という新しい浄化施設は、「高速凝集沈殿方式」という方式を採用したもので、浄化性能が高く、一日当たり最大2万トンの濠水を浄化する能力があるという。詳しく皇居外苑の濠水浄化施設についてという「国民公園協会 皇居外苑」のwebサイトにでていた。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/2000秒 34mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
19.大手門
桔梗濠に沿って歩いていくと大手門が見えてきた。大手門は城と城下町をつないだ江戸城の正門だ。1万石以上の大名と役高500石以上の役人以外は大手門の手前で乗り物を降り供回りは数人に制限されたという。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1600秒 52mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
20.皇居東御苑への入り口 大手門
桔梗濠と大手濠の間にかかる土橋の向こうに枡形になった大手門の高麗門(正門)がある。一行32名はここで守衛さんから入場証をいただき中に入った。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/640秒 32mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
21.大手門と渡櫓門
高麗門を入って枡形になった右手に石垣で囲まれた立派な入母屋造りの渡櫓(わたりやぐら)を持つ大きな櫓門がある。枡形門は、敵の侵入を防ぎ、味方の出撃を容易にする構造となっている。一の門(高麗門)は狭くて多勢では入れず、入ると三方の石垣から弓、鉄砲の攻撃ができるようになっていた。江戸時代も火災・震災のたびに再建されてきた。1957年の明暦の大火の際も10か月で再建された。1923年の関東大震災でも大破、2年後に渡櫓を解体し両側の石垣を築き直す大修理が行われた。太平洋戦争末期の1945年4月13日、渡櫓は全焼。1965~67年にかけて復元工事を行った。一方、高麗門はほぼ江戸時代の様子をとどめているそうだ。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1600秒 27mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
22.旧大手門渡櫓の鯱
1945年(昭和20年)4月、太平洋戦争戦災で焼失した旧渡櫓の屋根に飾られていた鯱。頭部に「明暦三丁酉」と刻んであることから明暦の大火(1657年)で焼失したのち再建された時に作られたと推定される。今の大手門渡櫓は1968年(昭和43年)に再建されたものと説明書きがあった。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/500秒 56mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
23.矢穴
大手門の石垣に残る矢穴である。矢穴とは石垣の石を切り出す際に大きな岩にミシン目のように穴を穿ち、鉄の矢を打ち込んだ穴だそうだ。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/400秒 75mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
24.大手門の門扉
大手門渡櫓門の門扉。蝶番を見てもとても古いようだ。戦災で全焼したときにはこの門扉も焼けたろうと思う。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 27mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
25.東御苑 同心番所
大手門の渡櫓門を出て左に歩いていくと右手に同心番所があった。城の奥の番所ほど位の上の役人が詰めていた。ここ同心番所は同心が詰め主として登城する大名の伴の監視にあたっていたという。この同心番所の手前が大手三之門の跡だそうだ。御殿の入り口であり、ここでで御三家(尾張・紀州・水戸の3徳川家)を除くすべての大名・役人は、駕籠をおりて徒歩にて入門した。この先左手に百人番所があり、右に中之門跡の石垣がある。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/250秒 18mm ISO500 ) 露出補正 なし
|

|
26.中之門跡
ここから江戸城の雰囲気が変わるとガイドさんが説明してくれた。ネットの竹橋ガイドというサイトによると、この中之門の石垣は1638年(寛永15年)にその原形が普請され、1657(明暦3)年の明暦の大火で焼け、1658(万治元)年に熊本藩主・細川綱利により再構築され、1703(元禄16)年に起きた地震でも被害を受け、翌年に鳥取藩主・池田吉明によって修復された。その後、明治政府によって取り壊されたという説と、関東大震災で大破したまま再建されなかったという説を聞いたが、確認できいないとのこと。傍に建てられていた説明札では、皇居内の石垣は特別史跡「江戸城跡」に指定されている。「本丸中之門石垣」修復工事は平成17年8月~平成19年3月にかけて行われた。石垣は江戸城の中でも最大級の巨石が使われ布積みという技法で積まれている。この中之門石垣には本丸御殿への登城口として渡櫓門が配置されていたと解説されている。また、石垣は白い花崗岩と黒い安山岩とで築かれていて、白い花崗岩は瀬戸内の犬島か小豆島あたりから、黒い安山岩は東伊豆から運ばれたものであるそうだ。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 26mm ISO500 ) 露出補正 なし
|

|