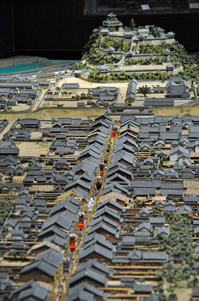宮ケ瀬ダムから道志みちを山中湖へ(1) 宮ケ瀬ダム 11月7日
本題に入る前にちょっとお知らせがあります。
10月29日から4回にわたり、「犬山、郡上八幡、白川郷、飛騨高山 古い町並みを歩く」というタイトルでバスツアーをした時のことをアップしていますが、サイト・オーナーのn-shuheiさんにより、その時の行程図、およびその行程で訪れたところの写真を開いて見られるような「国内旅行地図」を作成していただきました。
「Studio YAMAKO」のトップページを下へスクロールしていっていただくと、右側のカレンダーの下に、過去記事タイトルリスト、Category、・・・ と続き海外旅行地図、国内旅行地図と出てきます。その国内旅行地図の一番下の「犬山、郡上八幡、白川郷、飛騨高山 古い町並みを歩く Bustour」 を左クリックしていただくと、その時の行程の地図が開きます。地図上のマークを左クリックすると、左側にその地の写真が表示され、その写真をクリックすると大きな写真になり、そこで撮った写真すべてが右側の→で順次開いていきます。
「犬山、郡上八幡、白川郷、飛騨高山 古い町並みを歩く」以前の「国内旅行地図」でも地図上のマークをクリックして写真を開いていけたのですが、今回のはとても快適に写真を見にいけるようになりました。n-shuhei さんに感謝です。
さて、紅葉にはまだ少し早いかなと思いつつ、天気も良いので、かねてから一度走ってみようと思っていた国道413号線で山中湖へ行ってみることにした。途中、ここも一度行きたいと思っていた相模原の宮ケ瀬ダムに寄り道をする。
自宅を7時過ぎに出発し、圏央道の相模原相川ICを目当てに進んだ。そこから一旦R412を走り、半原というところを左折し、「宮ケ瀬ダム水とエネルギー館」の駐車場に8時半に到着した。駐車しようとしたところ、開場は9時からだという。受付の係りのかたが親切な人で、トンネルをふたつ抜けると5分ほどのところに「宮ケ瀬湖畔園地」があるので、そこで時間を潰して戻ってきてくださいという。人影のない「宮ケ瀬湖畔園地」を30分ほど観て、「宮ケ瀬ダム水とエネルギー館」の駐車場に戻ってきた。宮ケ瀬ダムの堤頂からエレベータでダムの下に下りた。宮ケ瀬ダムの少し下流にある石小屋ダムというのが思いのほか印象的だった。
10時半を過ぎたところで、再びエレベータで堤頂に上がり、駐車場を出発した。しばらく県道64号線を北へ進み、牧野というところで国道413号線に入り、道志川沿いに西へと走る。
|
1.宮ケ瀬湖畔園地 「宮ケ瀬やまびこ大橋」を渡った先の信号を県道64号線へと右折したところで車を止めた。そこから、これから渡っていく「水の郷大つり橋」を右手に見る。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
2.水の郷大つり橋 「水の郷大つり橋」を渡る。遊覧船のりばの桟橋をまたいでかかっている。橋の長さは315m、歩行者専用の大きな吊り橋だ。 宮ヶ瀬湖の湖面を散歩するする気分で渡っていく。イルミネーションを取り付ける作業が行われていた。クリスマスシーズンにはイルミネーションが点灯するそうだ。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
3.けやき広場 「水の郷大つり橋」を渡ると「けやき広場」があった。2.5haあるという芝生が広がる広場だ。 広場のまわりにけやきの木が植えられている。正面は石段になっていて、そこに座ってこちら側を眺めると、広場の先に宮ケ瀬湖が眺められそうだ。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/320秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
4.水の郷交流館 平日の朝9時とあって人影は見られない。遠くから眺めただけだが、この建物は「水の郷交流館」といい、水没した宮ケ瀬地区の文化を懐かしみ、伝承する展示や、集会場などがあるという。色づいた木々が美しい。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/160秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
5.宮ケ瀬ダム 堤頂 9時を過ぎたので車に戻り、「宮ケ瀬ダム水とエネルギー館」の駐車場へ戻った。今日は月曜日なので「宮ケ瀬ダム水とエネルギー館」は休館である。駐車場に車を止めさせていただいて、宮ケ瀬ダムの堤頂に向かう。左手に相模川水系の中津川が堰き止められた宮ケ瀬湖が広がる。宮ケ瀬ダムは1971年に着工し、2000年(平成12年)に完成した。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f5 1/250秒 40mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|
|
6.宮ケ瀬ダム インクライン 宮ヶ瀬ダムインクラインは、工事中に活躍したダンプトラック搭載型インクラインの一部を活用し設置されたケーブルカーだそうだ。ダム上下(山頂-山麓)までの移動手段として利用されている。6分~10分間隔で運行され、定員は46名、大人往復300円だが、月曜日は運休だった。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f6 1/250秒 155mm ISO560 ) 露出補正 なし |

|
|
7.ダム下流とインクライン 堤頂よりダム下流を眺める。手前に見えるのがインクライン。先に記したように、宮ケ瀬ダム建設では堤体コンクリートの打設のために大規模なインクラインが設置された。20トン ダンプトラックを運べる能力があり、コンクリートの運搬や資機材の移動に威力を発揮し、工期短縮に貢献したという。その一部は完成後、見学客用に残されており、先に記した通り乗車券を買って誰でも乗れるのだ。incline を辞書で引いてみると「傾斜」を意味するようだ。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/250秒 48mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|
|
8.堤頂からの眺め 宮ケ瀬ダムの堤頂から厚木方面、さらに相模湾方面を眺めた。曇り空ですっきりしない。SIGMA 18-300mm は良いレンズと思うが、絞り開放では焦点距離130mmでも周辺光量不足が目立つ。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f6 1/250秒 130mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|
|
9.堤頂部 宮ケ瀬ダムの堤頂部を歩く。この日はインクラインが動いていないので、エレベータでダムの下へ降りることにした。インクラインは有料だが、エレベータは無料だった。その先に見える展望塔にも上ってみたが、そこからの眺めは堤頂部から見る景色とあまり変わりはなかった。アクリル板越しに眺めることになるが、そのアクリル板には傷と汚れがあり、クリアではなかった。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/250秒 78mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
10.ダム下流 ダムの下をのぞき込むと真下にあるのが「愛川第一発電所」だ。第一発電所の最大出力24,200kWで電力需要の多い時間帯にピーク式発電を行うそうだ。日本最大の奥只見発電所の560,000kWに比べると規模は小さい。その下流(写真右中央)にアーチ形の新石小屋橋が見える。さらにその下流に「石小屋ダム」(写真右上)が見える。水の色が美しい。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/250秒 32mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|
|
11.宮ケ瀬ダム正面 エレベータでダムの下に下りた。このときは放水されていなかったが、大きなダムだ。このダムの目的は中津川・相模川中下流部の洪水調節、沿岸農地への慣行水利権分の農業用水補給・中津川における河川生態系保全のための河川維持放流を目的とした不特定利水、横浜市・川崎市・相模原市等神奈川県全体の2/3の地域、県人口の90%への上水道供給、直下流に併設された神奈川県企業庁の愛川第一発電所による最大出力24,000kWの水力発電と記されている。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
12.大沢の滝 愛川第一発電所の前を通って、石小屋ダムの方へ歩いていくと新石小屋橋の右側に大きな滝があった。落差40mの「大沢の滝」という。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/250秒 52mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|
|
13.新石小屋橋から宮ケ瀬ダムを望む
ダムの右側の木々が紅葉の名所となっている。まだ少し時期が早かった。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/250秒 32mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|
|
14.ロードトレイン「愛ちゃん号」 隣接してあいかわ公園があるが、そのあいかわ公園の入り口近くのパークセンターと宮ヶ瀬ダム下間(片道1km 約7分間)を結ぶシャトル便として、イタリア製のロードトレイン「愛ちゃん号」が走っている。まだ、待機中だった。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/250秒 46mm ISO360 ) 露出補正 なし |

|
|
15.石小屋ダム 宮ケ瀬副ダム 石小屋ダムは宮ケ瀬ダムの副ダムである。宮ケ瀬ダムとは趣の違う優美なダムだった。石小屋ダムには、愛川第二発電所があり、最大出力1,200kWで、この発電所の24時間連続運転による発電で、下流の中津川の河川維持用水など必要な水量を安定的に放流するという役割を担うという。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/250秒 24mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
16.石小屋ダム 石小屋ダムからさらに少し下流へ歩いてみた。石小屋ダムがある場所はかつて中津渓谷と呼ばれた景勝地であったが、ダム建設によって大きく姿を変えた。周辺はダム遊歩道や県立あいかわ公園として整備され、新たな観光地となっている。中学生のころ(1956年?)だったと思うが蝶仲間とともにギフチョウを捕りに、本厚木からバスに乗って中津川渓谷へ来たのを覚えている。その時は1頭だけだったがギフチョウを捕った。その時のギフチョウは私の古い標本箱に残っている。その後の開発により中津川のギフチョウは絶滅してしまった。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/250秒 24mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|
|
17.石小屋ダム堤頂 これは石小屋ダムの堤頂部に架かる橋だ。左側の岩には「石小屋橋」、右側の岩には「石小屋湖」と刻まれていた。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f5 1/250秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|
|
18.石小屋橋を渡る 石小屋ダムの堤頂部にかかる石小屋橋を反対側へ渡ってみた。石小屋湖に貯えられている水の青緑色のパステルカラーがきれいだ。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/250秒 20mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|
|
19.「ふれあい広場」からみた宮ケ瀬ダム あいかわ公園の入り口のパークセンターからくると、この辺りで宮ケ瀬ダムを見ることになる。
Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/250秒 35mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|
|
20.石小屋湖 宮ケ瀬ダムの下流、石小屋ダムのダム湖は石小屋湖と名付けられている。木が焦げたように黒くなっている。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/125秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
21.紅葉の名所 宮ケ瀬ダムの下、左岸の木立は神奈川県の紅葉名所にあげられている。見ごろは11月の下旬だろうか。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/160秒 23mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
22.宮ケ瀬湖 再びエレベータで堤頂へ上がった。駐車場へ戻る途中、ダム湖である宮ケ瀬湖を眺めた。神奈川県秦野市の北部に位置する丹沢山地のヤビツ峠(標高761m)付近を源とし北流する中津川を堰き止めた宮ケ瀬湖の総貯水容量は約2億トンで、奥多摩湖(小河内ダム)や奥利根湖(矢木沢ダム)に次ぐ関東屈指の大ダム湖である。向こうに見えるのは陣馬山に続く山並みであろう。。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 20mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|