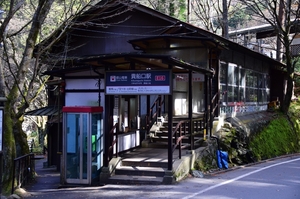コロナ禍の浅草 7月6日
緊急事態宣言と国民の自粛、協力、貢献が効果を発揮し、感染者数の増加も止まり、6月19日にほぼ全面的に自粛が解除された。そんな時、大学時代のクラスメートから、「土用も近いので鰻でも食べようよ」とメールが届いた。二つ返事で同意し、7月6日に3人で浅草の操業220年という老舗のうなぎ屋で会食をすることが決まった。
夕方5時から始めることにしたので、早めに浅草に行き、少し歩いてみようと思った。梅雨時の平日の夕方ということで、普段でも観光客は少ないのかもしれないが、それにしても人出が少ないのに驚いた。「仲見世通り」も閉めている店がある。
サクラの頃など、何回か浅草に来ているが、その頃は、もちろん大勢の参拝者、観光客が溢れていた。あまりゆっくりと、あちこち見て歩いた記憶がない。この日、ほんの30分から40分くらいだったが、コロナ禍の浅草を歩いてみた。
6月24日から1週間ほど、東京の1日あたりの新たな感染者が50人を超えるような日が続いている。さらに7月9日、10日と東京都内の新たな感染者数は200名を超えた。急激に感染者数が増加することがないように祈るばかりだ。
|
1.雷門 横浜から京浜急行、都営地下鉄浅草線直通の特急電車に乗って、浅草で下りた。雷門方面の案内に従って、地上に出る。さて、雷門は何処かと探す。どうやら右手が吾妻橋で、左手の雷門通りの信号を渡ったところが雷門だ。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/320秒 25mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
2.雷門から仲見世を見る スクランブル交差点を渡って雷門の前に行く。人は本当に少ない。こんな浅草を見たことがない。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 25mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
3.雷門 立てられている説明板によれば、天慶5年(942年)、平公雅 によって創建されたのが始まりだそうだ。現在の門は慶應元年(1865年)の浅草俵町の大火で炎上した門に代わり、昭和35年に松下幸之助さんの寄進により復興した。シンボルである赤い大きな提灯には、「令和二年四月吉日」とある。2013年に5基目が新調されたあと、2020年に6基目として新調されたが、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、奉納式は中止された。松下電器産業株式会社 現パナソニック株式会社 創業者 松下幸之助の銘が入っている。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/100秒 14mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
4. 風来神門 同じく説明板によれば、雷門は「風来神門」と呼ばれる。門の正面向かって右に「風神」、左に「雷神」を祀る。このことから「雷門(風雷神門)と呼ばれるという。ともに鬼面蓬髪、風袋を担いで天空を駆ける風神と、虎の皮の褌を締め連鼓を打つ雷神の姿はお馴染みのものだ。門の裏側には、向かって右に「金龍」、左に「天龍」の龍神像が祀られ、これら四神は、浅草寺の護法善神として、伽藍守護・天下泰平・五穀豊穣の守り神とされる。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/100秒 11mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
5.「仲見世通り」 梅雨時の平日の午後4時過ぎと言えども、何と人の少ない仲見世通りだろう。wikipediaによれば、"雷門から宝蔵門に至る長さ約250mの表参道の両側には土産物、菓子などを売る商店が立ち並び、「仲見世通り」と呼ばれている。商店は東側に54店、西側に35店を数える。"
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 32mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
6.浅草文化観光センター はじめは、雷門と「仲見世通り」の様子を見て、今夜の会食の店である うなぎ屋「やっこ」へ行こうと思っていた。スカイツリーが見えるかと思い、雷門通りを反対側に渡ろうとしたとき、このユニークな建物が目に入った。かって、この地には、2階建の銀行の建物があり、1985年に台東区が買い取って浅草文化観光センターを開設したそうだ。その建物が築50年を過ぎ老朽化が進んだことから2008年にコンペが行われ、隈研吾の案が採用されて2012年に完成したのがこの斬新な建物である。総事業費は約16億円と言われる。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 11mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
7.東京スカイツリー 右手、隅田川の向こうに東京スカイツリーが見えた。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 23mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
8.車やさん 雷門の前に来ると、人力車が観光客を乗せて走り出す姿を良く見てきた。しかし、コロナ禍の今、人力車の呼び込みの姿は見えるものの客はなく、手持無沙汰のようだ。ここには「えびす屋」「時代屋」「くるま屋」といったいくつかの車やさんがあるようだ。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/250秒 37mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
9.「新仲見世通り」 今宵行くうなぎ屋さんは、雷門通りを西に行った田原町に近いところだ。再び、雷門通りを反対側に渡って、田原町に向かって歩き出すと「浅草中央通り」という筋があたので、誘われるように右折すると「新仲見世通り」にでた。うなぎ屋さんでの集合時間にまだ少々時間があったので、賑やかな右の方に歩いてみると、「仲見世通り」と交差した。「新仲見世通り」 は100店舗、380mに及ぶ大きな商店街で、ここは人通りも多かった。ひとことで言うと、江戸の仲見世、昭和の新仲見世だそうで、浅草最大の商店街とのこと。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/250秒 37mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
10.「仲見世通り」の裏側 そこから「仲見世通り」の裏側が見える。寺院建築風の外観を持つ店舗は、関東大震災による被災後、大正14年(1925年)に鉄筋コンクリート造で再建されたものだそうだ。浅草寺は付近の住民に境内の清掃を賦役として課すかわりに、南谷の支院の軒先に床店(小屋掛けの店)を出す許可を与えたのが貞享2年(1685年)頃のことで、これが「仲見世通り」の発祥といわれているそうだ。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/200秒 30mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
11.静かな「仲見世通り」 もう一度時計を見る。まだ少々余裕があるので、浅草寺さんにお参りして行こうと思う。参道である 「仲見世通り」を進む。閉じている店のシャッターの絵が良い。営業中の人形焼きの店があった。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/320秒 11mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
12.「伝法院通り」 左手に 「伝法院通り」があった。伝法院は 宝蔵門の手前西側にあり、浅草寺の本坊である。小堀遠州の作と伝えられる回遊式庭園がある。通常、一般には公開していないが、特別公開されることがある。平成23年(2011年)、国の名勝に指定された。院内にある天祐庵は表千家不審庵写しの茶室で、江戸時代後期の建立。もとは名古屋にあったという。伝法院通りは延長150mほどの商店街で、片側が伝法院に面しているところからこの名が付けられたそうだ。明治の中頃、すでに商店街を形づくっていたという。それだけに商店会が生れたのは古く、大正15年とのこと。伝法院通りには街を飾る「だじゃれ看板シリーズ」など色々な装飾がある。写真で下馬の札の上に見える看板は「ねたものふうふ "にたもの夫婦"」と読み取れる。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/400秒 22mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
13.宝蔵門 「仲見世通り」がおわると宝蔵門がある。立派な門だ。入母屋造の二重門は2階建てで、外観上も屋根が上下二重になっている。現在の門は昭和39年(1964年)に再建された鉄筋コンクリート造で、実業家・大谷米太郎夫妻の寄進によって建てられたものだそうだ。かつては「仁王門」と呼ばれていたが、昭和の再建後は宝蔵門と称している。その名の通り、門の上層は文化財「元版一切経」の収蔵庫となっているという。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 12mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
14.宝蔵門と五重塔 宝蔵門の手前から、左側に五重塔が見えた。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 12mm ISO400 ) 露出補正 +7段 |

|
|
15、「小舟町大提灯」と「魚がし」吊り灯篭 宝蔵門の「小舟町大提灯」は、日本橋小舟町の商人からの奉納提灯だそうだ。日本橋の魚河岸信徒の心意気を示したもので、小舟町では、1659年に奉納したことに始まり、その伝統を江戸時代から現代へと連綿と受け継いできているという。前回は、江戸開府400年にあたる2003年に奉納された。現在の提灯は2014年10月に奉納され4回目の掛け替えがされたという。右側の「魚がし」吊り灯篭は、高さ 2.75m、重さ 1.000kg 銅製で、魚がし講(同一の信仰を持つ人々による結社)より昭和63年(1988年)10月、2回目の奉納掛け替えがされている。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/200秒 16mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
16.宝蔵門の大わらじ 宝蔵門の背面左右には、魔除けの意味をもつ巨大なわらじが吊り下げられている。これは、宝蔵門の仁王像の作家である村岡久作が山形県村山市出身である縁から、同市の奉賛会により製作奉納されているもので、わら2,500kgを使用しているそうだ。 わらじは仁王さまのお力を表し、「この様な大きなわらじを履くものがこの寺を守っているのか」と驚いて魔が去っていくといわれている。宝蔵門のわらじは10年おきに新品が奉納されている。また、寺院の山門には一対の大わらじがかけられていることがあるが、これは仁王様が履いていたわらじを脱いで掛けてあるという建前らしいとも。一昨年、滋賀県の湖東三山を訪れたが、百済寺、西明寺、金剛輪寺の山門にもわらじがかけられていた。湖東三山はいずれも天台宗の寺院である。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/200秒 9mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
17.五重塔正面 天慶5年(942年)平公雅が塔を建立したと伝わる。この塔は三重塔であったといわれる。焼失を繰り返したのち慶安元年(1648年)に五重塔として建立された。本堂と同様、関東大震災では倒壊しなかったが昭和20年(1945年)の東京大空襲では焼失した。戦前までの塔は、今と反対側の本堂に向かって右側にあった。現在の塔は昭和48年(1973年)に再建されたもので鉄筋コンクリート造、アルミ合金瓦葺き、基壇の高さ約5メートル、塔自体の高さは約48メートルである。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 12mm ISO400 ) 露出補正 +0.7段 |

|
|
18.浅草寺本堂 後先になってしまったが、wikipediaによれば、 浅草寺の山号は金龍山 。本尊は聖観世音菩薩。元は天台宗に属していたが、昭和25年(1950年)に独立し、聖観音宗の本山となった。観音菩薩を本尊とすることから「浅草観音」あるいは「浅草の観音様」と通称され、広く親しまれている。都内では、唯一の坂東三十三箇所観音霊場の札所(13番)である。江戸三十三箇所観音霊場の札所(1番)でもある。全国有数の観光地であるため、正月の初詣では毎年多数の参拝客が訪れ、参拝客数は常に全国トップ10に収まっている。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 13mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
19.本堂正面 参拝者の数は少なかった。旧本堂は慶安2年(1649年)の再建で近世の大型寺院本堂の代表作として国宝(当時)に指定されていたが、昭和20年(1945年)の東京大空襲で焼失した。現在の堂は昭和33年(1958年)に再建されたもので鉄筋コンクリート造である。再建にあたっては、建設資金を捻出するために瓢箪池の敷地(2400坪)が江東楽天地などに売り払われたといわれる。掛けられている「志ん橋大提灯」は新橋の方々(花街?)からの奉納提灯で、平成16年12月に制作し寄進された。 江戸時代の浮世絵師・広重「浮絵浅草寺雷門之図」には、新橋から奉納された、「志ん橋」大提灯が描かれているという。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/250秒 9mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
20.本堂外陣と内陣 本堂の石段を上がってみると、478.5m2(145坪)の外陣があり、その向こうに、幅 12.7m・奥行 14.5m、226.9m2(68.75坪)60畳敷と内々陣黒漆塗鏡の間がある。中央に川端龍子画「龍之図」(縦6.4m・横4.9m)、左右に堂本印象画「天人之図」(縦6.4m・横4.9m)という外陣の天井画が見事だった。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/40秒 9mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
21.21時の雷門 創業200年以上、勝海舟も通ったという うなぎ屋「やっこ」に着いたのは集合時間ギリギリの午後5時で、クラスメートの2人は既に座っていた。コロナ厄払いの浅草寺お参りを口実にギリギリになったことを詫びた。それから3時間以上、楽しい時間を過ごしたが、酒も美味かったし、友人が持ってきてくれた「響17年」も美味かった。白焼き、かば焼き、うざくなど、ぜいたくな酒の肴も美味しかった。結局、うな重はお土産になってしまった。8時半お開きにして、浅草駅へ歩く途中の雷門は静まりかえっていた。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/60秒 18mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|