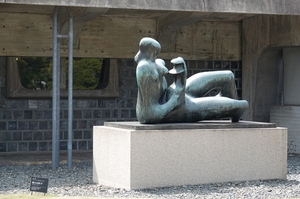保土ヶ谷歴史散歩 (前編) 1月20日
過日、保土ヶ谷区役所へ住民表を取りに行く用事があった。書類ができるのを待つ間、待合室の棚に並べられている印刷物を見ていたら、「保土ヶ谷の歴史的建造物巡り」パネル展のパンフレットがあった。天王町の「岩間市民プラザ」で2月3日~2月10日に開催される。興味を持って、インターネットで関連情報を検索してみた。
その中に「保土ヶ谷歴史まちあるき 2017」という横浜市保土ヶ谷区のサイトがあった。そのサイトにあるPDFのパンフレットを参考に歩いてみようと思った。2月3日からの「岩間市民プラザ」の展示を見てからでも遅くはないのだが、少し歩きたかったので、そのMapに従って回ってみることにした。
パンフレットによれば、そのコースはA.旧東海道まちかど博物館めぐり(約2.7km)、B.洋館堪能コース(薬2.0km)、C.保土ヶ谷宿と洋館巡りコース(約2.6km)と3っあったが、できるだけ歩いてみようと思う。予定としては、10時に家を出発して午後2時帰宅だった。
実際に歩いたコースは、まず、旧古町橋跡からAコースに入り、パンフレットの道順とは逆回りだが、初詣に行く神明社に出て、大門通りをその天王町寄りの相州街道(大門通り)入口から旧東海道に入る。この辺りはお寺が多い。環状1号に出て、NS邸という歴史的建物を見て、遍照寺にお参りし、再び環状1号に出る。
環状1号を保土ヶ谷駅方面へ歩き、保土ヶ谷駅の手前を右に、旧東海道を歩く。横浜帷子郵便局を右に曲がって、坂道を登っていく。息が切れる。住んでいる人たちは大変だなと思う。いくつかの歴史的建造物である洋館を見て、月見台の頂上に出た。
|
1.古町橋からスタート この日の保土ヶ谷歴史散歩は、いつも冬の水鳥を撮りに行く帷子川に架かる古町橋からスタートした。古町橋を渡ると相鉄線の踏切がある。昨年11月24日に高架線が開通し、今は踏切の線路はなくなった。星川からの高架線が天王町の高架駅に繋がっている。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
2.旧古町橋跡 少し進むとこんな案内板が建てられていた。この場所には江戸時代初期の東海道が帷子川を渡る「古町橋」があったそうだ。かねてから暴れ川として反乱を繰り返していた帷子川の改修が昭和38年に決定され、帷子川の流路は北側に移された。さっき渡ってきた古町橋は昭和41年(1966年)に架設されている。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
3.相州道 今は大門通りと呼ばれているが、ここで旧東海道と分かれる。大門通りはバス通りで、写真に見える保土ヶ谷駅方面に向かう細い道が旧東海道だ。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
4.天徳院 ここから先にはいくつかのお寺がある。寺町なのだろうか。まず、天徳院というのがあった。 天徳院は曹洞宗の寺で山号を神戸山という。(保土ケ谷区役所資料歴史を歩いてみよう)によれば、 開山は安土桃山時代(1573年)。本尊は運慶作といわれる地蔵菩薩坐像。土地の豪族、小野筑後守が帰依して建立した。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
5.天徳院本堂 山門を入ると本堂がある。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 21mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|
|
6.天徳院 地蔵 お地蔵さんが3体祀られていた。隠れて見えないがこの3体の地蔵の向こうにも、小さな地蔵が3体あった。そのうち1体は子供のようだ。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 12mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|
|
7.見光寺 山門 すぐ近くに見光寺という寺院があるのだが、なかなか見つけられなかった。「猫の足あと 横浜市寺社案内」というサイトが参考になるが、見光寺は、保土ヶ谷の住人で熱心な浄土宗の信者、茂平夫妻(道意)が開基となり寛永6年(1629年)に創建、深川靈巖寺第三世大誉珂山上人(寛文11年1671年寂)が開山したという。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 17mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|
|
8.見光寺 六地蔵 不勉強であるが、6体並んだ地蔵を見ることがしばしばある。wikipediaによれば、六道の思想に基づいて地蔵菩薩の像を6体並べて祀られたもので、各地で見られるとある。六道とは、仏教において、衆生がその業の結果として輪廻転生する6種の世界(あるいは境涯)のこと。六趣、六界ともいう。六道には天道、人間道 、修羅道、畜生道、餓鬼道、 地獄道だそうだ。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 17mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|
|
9.見光寺 本堂
山門から本堂が見える。この本堂は比較的新しく建てられものではなかろうか。本尊は阿彌陀如來坐像。保土ヶ谷出身のコラムニスト青木雨彦氏の句碑があることを後で知ったが、その時は知らずに通り過ごしてしまっていた。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|
|
10.天徳院山門 見光寺から一旦環状1号線に出た。保土ヶ谷方面に進んで右側の細い路地の先に天徳院山門が見えた。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|
|
11.NS邸 元米穀商 -1 天徳院山門が見えた環状1号線沿いに、歴史的建造物に一つであるNS邸が見えた。この建物は元米穀商大岡米店で昭和6年建築の木造2階建ての町屋である。旧保土ヶ谷宿沿道に残る唯一の町屋(商家)だそうだ。現在は住宅になっている。旧宿場通りの歴史的景観を偲ばせる建物として貴重である。お隣の蕎麦やさんも、その看板といい、なかなか渋い。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 14mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|
|
12.N邸 元米穀商 -2 旧宿場通りの歴史的景観を偲ばせる建物として貴重である。表札も出ているのでお名前は分かってしまうのだが、NS邸とさせていただいた。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 10mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|
|
13.今井橋 今井川にかかる今井橋。今井川は帷子川の支流である。JR東海道本線と国道1号に沿って市街地を東に流れ、天王町駅付近で相鉄本線をくぐり、西区との区境に近い岩間町・西久保町の境で帷子川に合流する。これは上流である保土ヶ谷方面を撮っている。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
14.旧中橋跡 かって今井川はこの宿場を横切っていて中橋が架けられていた。その川筋は慶安元年(1648年)に新しい保土ヶ谷宿が建設された際に人工的に造られたものだった。しかし、その流路の構造から大雨の際にここで水が滞り、しばしば下流域を浸水することになったが、なかなか改善されなかった。しかし、幕末になって人馬の往来が急増してきたため嘉永5年(1852年)宿場では改修費用100両を準備するとともに町役人が200両の借用を代官に陳情し認められると、すぐに現在の川筋に改修されたといったことが説明されている。また、看板だけの写真になってしまった。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
15.遍照寺山門 旧中橋跡の少し北側に医王山遍照寺という高野山真言宗の寺院があった。遍照寺の創建年代等は不詳ながら、貞観18年(876年)に眞雅僧正が開創したと言われる。慶興法印が元和4年に峯岡から当地へ移し中興したという。本尊の薬師如来像は横浜市指定文化財。念仏百万遍の供養塔や、岡野新田を開拓した岡野家の墓所がある。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
16.遍照寺 真雅会館涅槃堂 山門を入ると正面に本堂があるが、その参道の右側に、真雅会館涅槃堂という立派な建物が建っていた。要は葬儀(通夜、告別式)および法要施設である。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 12mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|
|
17.遍照寺 本堂 見たわけではないが、「猫の足あと 横浜市寺社案内」には本尊の木造薬師如来坐像は、量感に富み、目鼻立ちの整った面部は張りが強く、運慶の作風を示していると記されていた。面長の顔だちや左肩に大きな折返しをつくった着衣の形式に宋元風の影響も認められる。市内に伝わる当代の彫刻の中では屈指の佳作だそうだ。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 13mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|
|
18.帷子会館 再び環状1号線に戻る。遍照寺から環状1号線に出てきたところに帷子会館があった。「保土ヶ谷歴史まちあるき」のパンフレットには帷子会館は大正初期の建築で、木造平屋建てで近代洋風である。当初は消防署の消防車を収納していた建物であった。現在は町内会館として利用されている。棟にレトロ感漂う板金製フィニュアルを載せ、印象的な妻壁のアーチ付き換気ガラリが2っ並び、木組みの腕木に支えられた庇が付いている。大正期の建物として旧東海道沿いに残る稀有な洋風建物である。歴史的建造物の良い保存活用例とされると説明されている。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 23mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|
|
19.環状1号線の歩道 環状1号線の歩道 の敷石に、こんな絵柄のブロックが埋め込まれていた。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|
|
20.NJ邸 元旅館業 横浜帷子郵便局へ曲がるところで、A.旧東海道まちかど博物館コース は終わる。少し保土ヶ谷駅よりに入ったところに第二常盤湯という戦後復興期の昭和28年に建てられ、現在でも営業している銭湯があったのだが、見落としてしまった。まちかど博物館というのは、保土ヶ谷で積み重ねられてきた歴史、生活文化、生業の技を物語るものが展示されている時計屋さん、石材店、薬局などの商店のことである。さて、ここから月見台という高台に向けて洋館堪能コースとなるのだが、横浜帷子郵便局のところを左に入ったところに、このNJ邸があった。大正13年建築で木造平屋建ての洋館付き住宅である。昭和28年ごろ増改築をして平成17年ころまでは旅館業を営んでいたという。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|
|
21.E邸 -1 昭和34年に建てられた木造2階建ての洋館付き住宅である。数少ない戦後に建てられた洋館付き住宅で、その特徴が良く判る。低い軒高、緩い勾配のフランス瓦屋根、横長の開放的な窓の洋館と和館からなる。表札もかけられていて、まどのカーテンは閉められているが、住まわれているようだ。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|
|
22.E邸 -2 ここからは、和館の部分が眺められる。よく手入れされて眺めも良い庭からも横浜港を一望できるそうだ。良好な景観を呈する。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
|
23.S邸 昭和4~5年頃建築の木造平屋建て洋館付き住宅である。この辺りは高台になり、高級住宅地である。モダンな平屋建ての洋風意匠と庭が昭和初期の月見台の住宅地景観を偲ばせる住宅である。周囲は新しい家が立ち並んでいるが、どの家もなかなかの景観であった。ここからさらに月見台のバス通りまで上るのだが、坂道が続く。ブログもここいらで一休み。
Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|