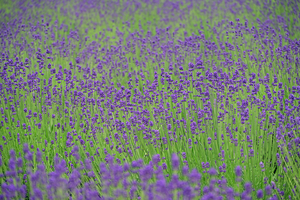|
1.ホンアジサイ(本紫陽花)
日本原産のガクアジサイの栽培種で、単にアジサイともいう。 花序のほとんどが装飾花からなる手毬咲き状のアジサイのこと。峰岡公園に写真のようなホンアジサイが咲くようになって、数日が経っている。装飾花が他のアジサイと違うようなので、何だろうと思っていた。アジサイに蝶が吸蜜に来るのは見たことがないが、前回この花の前を通ったときにヤマトシジミが吸蜜に来ていたようだった。品種名は調べられなかった。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
2.ムラサキバレンギク(紫馬簾菊) と ホンアジサイ
wikipediaによると、ムラサキバレンギクは北アメリカ原産の多年草。花期は初夏から晩秋にあたる7〜10月頃で、頭状花(花の中央に見える部分)は盛り上がり、舌状花(花弁に見える部分)はやや下向きに咲く。後ろのホンアジサイの品種名(あるいは呼称)は「白楽天」という花に似ているが、確信はない。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 37mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
3.モンシロチョウ♂
花壇にはモンシロチョウが数頭翔んでいた。花で吸蜜する個体は少なく、時々このように葉に止まって休んでいるように見える。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
4.ホンアジサイ
これもホンアジサイだと思う。だが、日本原産の品種をアジサイ、ホンアジサイと呼ぶのに対し、ガクアジサイが西洋で品種改良されたものを西洋アジサイ(ハイドランジア)と呼ぶそうだ。さまざまな色があり、日本古来のアジサイよりも見た目が豪華な品種が多いのが特徴という。難しい。これは、そのハイドランジアかもしれない。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
5.アガパンサス・プラエコクス
南アフリカ原産。日本では園芸用に球根が販売される。ヒガンバナ科 / ムラサキクンシラン属(アガパンサス属)。アガパンサスは和名をムラサキクンシラン(紫君子蘭)という。さわやかな涼感のある花を多数咲かせ、立ち姿が優雅で美しく、厚みのある革質の葉が茂る様子には力強さも感じられるという。南アフリカに10~20種ほどの原種が自生し、交配などにより300以上の園芸品種が育成されているそうだ。性質が強く、植えっぱなしでほとんど手がかからないので、公園などの花壇やコンテナの植え込みに利用され、また切り花としてフラワーアレンジメントにも使われているという。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
6.ノリウツギ(糊空木)
「Picture This」で検索してみるとノリウツギだった。wikipediaによると、「ノリウツギはアジサイ科アジサイ属の落葉低木で、樹高は2~3mくらいで、高いものは5mくらいになる」とあった。ノリウツギはアジサイの仲間だったのだ。箱根湿性花園に咲くノリウツギにはミドリシジミやアサマイチモンジ、オオウラギンスジヒョウモンなどが吸蜜に来る。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.7 1/1250秒 37mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
7.ムラサキバレンギク と モンシロチョウ
だいぶ擦れてしまったモンシロチョウが吸蜜していた。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.7 1/1250秒 37mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
8.ヤマトシジミ♂
いま、ヤマトシジミが多く翔んでいる。これも典型的な夏型の雄だ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/1250秒 37mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
9.ヒャクニチソウ(百日草) -1
和名のヒャクニチソウは開花期間が長いことに由来する。また、花の寿命が長いことからウラシマソウ(浦島草)やチョウキュウソウ(長久草)の別名もあるそうだ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
10.ヒャクニチソウ -2
ネットで調べてみると、「ヒャクニチソウの花は中心部の筒状花の部分とそれを取り巻く舌状花からなっている。 中心部の筒状花の部分は、長期間にわたって成長し、花を咲かせつつ上方に伸びる。 筒状花の花冠は黄色で5裂し有毛。 開花後に雌しべの柱頭が伸び、やがて柱頭だけがリボンのようになって残る。」と説明されていた。その通りの写真になった。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
11.ヒメヒオウギズイセン(姫檜扇水仙)
峰岡公園の反対側の花壇へ移動した。ヒメヒオオギズイセンは、アヤメ科ヒオウギズイセン属(クロコスミア属)の雑種。ヒオウギズイセンとヒメトウショウブとの交配種だそうだ。花茎から穂状花序を分枝し、各々に鮮やかなオレンジ色の花を付ける。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
12.ヒルザキツキミソウ(昼咲月見草)
マツヨイグサの仲間だ。北米原産の帰化植物であり、観賞用として輸入・栽培されていたものが野生化している。名称の由来は、宵に咲くツキミソウと違って、昼間にも開花していることによる。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 37mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
13.ハルシャギク(波斯菊)
和名の由来となっている「ハルシャ(波斯)」はペルシャのことだそうだ。別名はジャノメソウ(蛇目草)という。花の色は、中心が濃紅色で、周辺は黄色の蛇の目模様であり、別名のジャノメソウの由来となっているが、このほうが解りやすい。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
14.ムラサキギボウシ(紫擬宝珠)
ムラサキギボウシは半日陰や、日陰の湿った土壌を好む多年草で、カタツムリや、ナメクジが付きやすいそうだ。ギボウシとは、この植物のつぼみ、または包葉に包まれた若い花序が擬宝珠に似ていることに由来する。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
15.キンシバイ(金糸梅)
6月7日に舞岡公園へ行ったとき、古民家の裏庭で、見事に咲いていた。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
16.サルビア・コエルレア
サルビア・コエルレアは、メドセージという名前で流通している場合があるが、メドセージは本種とは別のものだそうだ。これは日本に入ってきた時に流通業者が勘違いしたことに起因する。優れた蜜源植物でありチョウやハチドリが訪れるという。昨年、北海道の美瑛を訪れたときに、咲いていたサルビア(来路花)に、エゾシロチョウが吸蜜に来ていた。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO400 ) 露出補正 なし
|

|
17.モモイロカイウ(桃色海芋)
始めて見た花だった。サトイモ科オランダカイウ属の園芸植物である。葉に斑が入らないのが特徴だそうだ。原産地は南アフリカで日本には大正初期頃に渡来しているそうだ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO320 ) 露出補正 なし
|

|
18.ビオラ・トリコロール
保土ヶ谷区役所に来た。1階駐車場の上にあるフラットな部分の周囲に花壇が設けられているが、そこにはパンジーなどが植えられている。地味だが可憐な花が咲いていた。「Picture This」 で検索すると、ビオラ・トリコロールとでた。ヨーロッパ原産の1年草で、本種を改良した園芸品種がビオラやパンジーと呼ばれ、流通している。紫、黄色、白の3色が混ざった花を咲かせるスミレであることから、ビオラ・トリコロールと名付けられたそうだ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO250 ) 露出補正 なし
|

|
19.ビオラ・コルヌタ<>br>
これも 「Picture This」 で検索した。日本でビオラと呼ばれている花は、ヨーロッパのピレネー地方原産のビオラ・コルヌタを中心に改良された園芸品種群であり、花の直径が4cm以下のものを指す。それより直径が大きい花はパンジーと呼ばれ区別されているそうだ。知らなかった。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO250 ) 露出補正 なし
|

|
20.ノウゼンカズラ(凌霄花) -1
保土ヶ谷区役所の前にある高層住宅の花壇に咲いていた。大きなオレンジ色の花が目立つ。凌霄花は漢名であるが、「霄(そら)を凌ぐ花」の意で、高いところに攀(よ)じ登ることによる命名という。漢詩では他の物に絡むため愛の象徴となるのだ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし
|

|
21.ノウゼンカズラ(凌霄花) -2
wikipediaによると、ノウゼンカズラの花は、枝先に円錐花序を萌出し、直径6-7cmの橙黄色の花を対生する。花房は垂下し、花冠は広い漏斗型で、先端は5裂し平開する。雄蕊は4本のうち2本が長い。日本では結実しにくいそうだ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO1250 ) 露出補正 なし
|