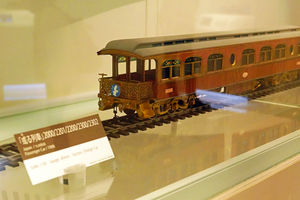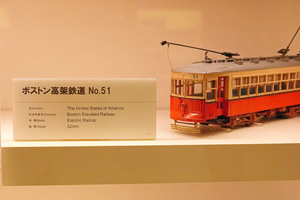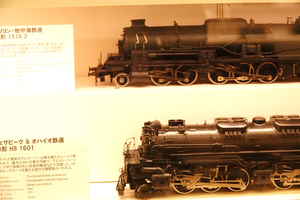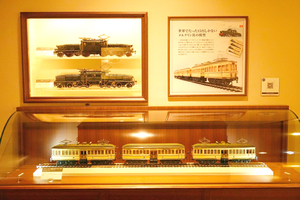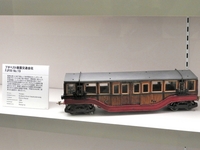ブダペストの午後は自由行動であったが、中央市場を見て、ヴァーツィ通りを歩き、カフェ・ジェルボーで一休みし、くさり橋を渡って、対岸を国会議事堂の正面まで行き、くさり橋の夕景を撮って、ドナウ川ディナークルーズの集合場所へ行った。歩き回ったので少々疲れてしまった。
15.ヴァーツィ通り
ゲッレールト温泉ホテルの外観を見て、再び自由橋を戻って、中央市場の前から、ブダペスト旧市街の目抜き通りであるヴァーツィ通りを歩いた。観光客が多く、レストラン、ブティック、土産物屋などが並ぶ。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/125秒 55mm ISO400 ) 露出補正 +0.3段
|

|
16.ヘレンド
ジョルナイ、ホロハーザとともに、ハンガリーの3大磁器に数えられる名品で、その名は日本でも知れ渡っている。1826年創業でハンガリー王室御用達となった直営店もあるが、ここはヴァーツィ通りのショップ。蝶の柄の磁器が私の目を引いた。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F5 1/125秒 75mm ISO400 ) 露出補正 -0.3段
|

|
17.カフェ・ジェルボー
中央市場からヴァーツィ通りを歩いてきたが、ヴルシュマルティ広場に抜けたところにあるカフェ・ジェルボーは、1858年創業の老舗カフェ。自由時間の休憩はここでしようと決めていた。ちょっと気取ってアイリッシュコーヒーを注文した。最近、東京の国道246号沿いの青山学院のあたりに店を開いたとのこと。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/100秒 36mm ISO3200 ) 露出補正 +1.0段
|

|
18.イシュトヴァーン大聖堂
キリスト教を国教に定め、後に聖人とされたハンガリー初代国王イシュトヴァーンを祭る大聖堂。1851年に建設が始まり完成まで50年を要したという。午後3時45分、だいぶ暗くなってきた。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/125秒 28mm ISO500 ) 露出補正 +0.3段
|

|
19.くさり橋を渡る
だんだんと暮れていく中、くさり橋をドナウ川対岸のブタ側に渡った。真中に灯りが見えるのは、王宮の丘を抜けるトンネルで、左側には王宮の丘へのケーブルカーの灯りが見える。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/125秒 52mm ISO800 ) 露出補正 -0.3段
|

|
20.国会議事堂 -1
17年の歳月をかけて1902年に完成したという。ハンガリーの歩みを象徴すべく、クラシック、ゴシック、バロック、ルネッサンスなど多彩な様式が組み込まれたという。対岸から夕暮れ時に撮りたいと思い、その正面までドナウ川の川岸を歩いて行った。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/125秒 38mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段
|

|
21.国会議事堂 -2
時刻は午後4時半過ぎ、前の写真から15分たった。中央の丸屋根がライトアップされた。空はかすかに明るさが残る。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/125秒 75mm ISO2500 ) 露出補正 0段
|

|
22.ライトアップされたくさり橋
撮りたかった夕闇のくさり橋だ。平凡な写真になってしまったが、三脚なしで撮るのに、F2.8と高感度の世話になった。ブタ側から撮った。時間は4時40分。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/125秒 28mm ISO2000 ) 露出補正 0段
|

|
23.くさり橋のライオン
くさり橋橋塔の各川岸側にはそれぞれ一対のライオン像がある。このライオン像には舌がない。造るときに職人が造り忘れたとか。まだ、空に明るさがほんの少し残り、橋はライトアップされて美しい。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/125秒 46mm ISO2500 ) 露出補正 +1.0段
|

|
24.ライトアップされた王宮
再びくさり橋を渡りペスト側に戻った。振り返って王宮の丘を見るとライトアップされて美しかった。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/60秒 28mm ISO3200 ) 露出補正 0段
|

|
25.ドナウ川ディナークルーズ
ディナークルーズの船に乗るため、6時30分にくさり橋の近くで集合になったが、それまでの時間は少々苦痛だった。午後はあちこち歩いたので疲れていた。仕方なく、近くのホテルに入り、ロビーで待機した。そして、ディナークルーズは夜の7時に出航になった。すっかり暗くなった。まずは、デッキに出て、くさり橋と王宮を撮った。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/100秒 48mm ISO3200 ) 露出補正 0段
|

|
26.再び国会議事堂
船は上流に向かって進み、国会議事堂のすぐ脇を進んで、マルギット島を回ってくる。これは横から眺めた国会議事堂である。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/60秒 55mm ISO3200 ) 露出補正 +0.7段
|

|
27.ゲッレールトの丘を望む
ちょっと自分の席に戻って食事をした。ブッフェ形式のディナーだったが、食べるよりも外の写真を撮るのに夢中になってしまう。これはくさり橋の上流から下流を眺めたところである。ゲッレールトの丘の、自由の女神が見える。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/30秒 28mm ISO3200 ) 露出補正 0段
|

|
28.自由橋とゲッレールト温泉ホテル
コースの最下流にきた。昼に渡った緑色の自由橋とゲッレールト温泉ホテル。この自由橋をくぐったところで、再び反転し、乗船したところに戻る。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/60秒 35mm ISO3200 ) 露出補正 +0.7段
|

|
29.ディナークルーズ船内
時間は8時30分、1時間半のクルージングは終わろうとしている。船内は食事の食器類もきれいにかたずけられて、客は談笑している。
Nikon D300 TAMRON 28-75mm F2.8D
プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/30秒 36mm ISO3200 ) 露出補正 +0.7段
|

|