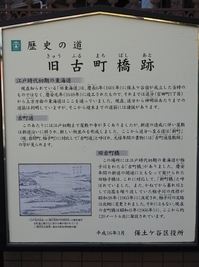2日ほど寒い日が続いたが、3月9日は快晴で暖かい日になった。とはいうものの、チョウが飛ぶにはまだ少し早い。しかし、窓から差し込む暖かそうな陽の光がじっとしてはいられなくさせる。というわけで、二俣川の近くにある、以前は大池公園と言われていた「こども自然公園」へ行って見ることにした。車で少しだけ横浜新道を走り、今井で下り、横濱カントリークラブの脇を通って、15分ほどで着いてしまった。近い。
駐車場は広く、私が停めた第一駐車場の収容台数は172台、料金は2時間で300円である。第2、第3駐車場もある。平日でもあったのでゆうゆう止めることが出来た。案内図を見て、大池の左側を歩く。まだ小さく、きれいな翅の色をしたカルガモが泳いでいる。橋を渡って、右手にキンクロハジロが泳ぐ中池を見てまっすぐ進み、第一の梅林に出た。ちょうど見ごろであった。保土ヶ谷公園では咲き分けが見られなかった「思いのまま」は見事に紅と白の花を咲かせていた。
最初の梅林の先を右手の進むと、「ピクニック広場」の手前右手に第二の梅林があった。ここでは、「枝垂れ緑咢」「大輪緑咢」「雪月花」「見驚」といった保土ヶ谷公園の梅園にはなかった品種の花を見ることが出来た。
1時間半ほどのんびりと散策を楽しんだ。ここはサクラもきれいなようなので、3週間後頃にはまた来てみようと思う。

|
1.大池のカルガモ
入り口広場に着いた。休憩舎やトイレがあり、その先には池が広がる。大池だ。大池にはカルガモが泳いでいた。昨年生まれたのだろうか、まだ小さな個体もいる。翅が鮮やかな色をしていた。カルガモの繁殖期は4月~7月にかけてだそうだ。 水辺の草の茂みに巣を作り、10~14個の卵を産む。 卵はメスだけで温め、26日ほどで孵化するという。池の端には、長いレンズを付けてカメラを構えた方々がいた。カワセミを狙っているらしい。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 34mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
2.ハト -1
以前にも、最近ハトが近寄っても逃げなくなったと書いたが、このハトも60cmくらい迄近寄って撮ることが出来た。140mmの望遠端で撮ったが背景がきれいにボケてくれた。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO250 ) 露出補正 なし
|

|
3.ハト -2
これは焦点距離33mmほどで撮ったが、背景が何か分かる程度にボケている。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO250 ) 露出補正 なし
|

|
4.中池のキンクロハジロ -1
中池にはキンクロハジロが多く泳いでいた。キンクロハジロは渡り鳥で、繁殖期は5~7月。日本では冬季に九州以北に越冬のため飛来する。北海道では少数が繁殖するという。写真の2羽は雌雄である。 繁殖期には後頭の羽毛が伸長するという。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 83mm ISO140 ) 露出補正 なし
|

|
5.中池のキンクロハジロ -2
キンクロハジロたちの一団が一列縦隊で中池を渡る。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 83mm ISO140 ) 露出補正 なし
|

|
6.梅林の入り口 「思いのまま」
中池の先に梅林があった。ウメの木の本数はそれほど多くはないが、見ごろを迎えていた。この「思いのまま」は紅白の花を見事に咲き分けていた。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 22mm ISO110 ) 露出補正 なし
|

|
7.「思いのまま」 -1
近寄って撮る。先日保土ヶ谷公園で見た「思いのまま」はあまり上手に咲き分けていなかったが、この木の花はまさに「おもいのまま」だった。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 63mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
8. 「思いのまま」 -2
さらに近づいて撮る。ピントを合わせる花の選択が難しい。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/800秒 140mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
9.「無類絞り」 -1
これは「無類絞り」という品種の花だ。淡い絞りが入った花が咲いていた。蕾がピンクで、開くと花びらの裏側にその色が残る。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/800秒 80mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
10.「無類絞り」 -2
「無類絞り」とは、これ以上はない最高の絞りという意味だそうだ。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
11.「無類絞り」 -3
蕾がピンクで、開くと花びらの裏側にその色が残る。よく見ると蕾にも絞りが入っているようだ。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/640秒 93mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
12.「無類絞り」 -4
絞りがはっきり表れている花にハナバチが来ていた。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO110 ) 露出補正 なし
|

|
13.月宮殿( ゲッキュウデン)
「月宮殿」という札がかかっていた。Webで検索してみたところ「かぎけん花図鑑」にヒットし、詳細を知ることが出来た。「かぎけん」とは、科学技術研究所のことのようだが、それ以上のことは分からない。「月宮殿」という品種は、花梅、野梅系野梅性、大輪(3-4cm)、八重咲き、乳白色で、15枚の抱え咲きの花を、比較的遅い時期(2月下旬~3月下旬)に咲かせる。花名はインドの古代宗教で、世界の中心とする「須弥山」の中腹を廻る月の宮殿からの命名という。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO280 ) 露出補正 なし
|

|
14.枝垂れ緑咢 -1
緑咢梅の枝垂れタイプだ。緑色をした蕾もよい。青軸性の八重咲の白梅枝垂れである。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 24mm ISO110 ) 露出補正 なし
|

|
15.枝垂れ緑咢 -2
まだ蕾が多いが、見事な枝垂れぶりだった。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f8 1/500秒 27mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
16.梅林の散策路
小型犬に散歩をさせている方が多かった。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f8 1/500秒 27mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
17.雪月花(セツゲツカ
)
比較的早咲きの品種で、開花時期は2月から3月。野梅系・野梅性の白い一重咲きの大輪で、花径は30mmから40mm。この品種名は桜や、山茶花にも存在し、更にサボテンなどにもあるので品種名だけでは紛らわしい。また、wikipedia には「雪月花」は日本の詩歌においては、これら三種(雪、月、花)を一度に取り合わせたものを指すものとしてしばしば用いられると記されていた。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f8 1/500秒 27mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
18.見驚(ケンキョウ)
見驚は梅の女王とも呼ばれる。淡い桃色の大輪の花は八重咲きで、見るものを驚かせるということから、見て驚かせる「見驚」と命名されたとのこと。 咲き始めは淡い紅色でやがて白花へと変化する。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f8 1/500秒 27mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
19.緑咢(リョクガク) -1
緑咢には、先ほどの「枝垂れ緑咢」とか「大輪緑咢」とか「緑咢春日野」とかいろいろ品種があるようだが、これは単に「緑咢」という。普通の白梅はガク(顎)が赤いのに対して、この花は顎が緑色なので「緑顎梅」と名付けられている。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f8 1/500秒 27mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
20.緑咢 -2
白い花と緑色の蕾の取り合わせが他の梅と一味違う。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 22mm ISO110 ) 露出補正 なし
|

|
21.大輪緑咢
この木には「大輪緑咢」という札が掛かっていた。緑咢とつく品種は、新しい枝も淡い緑色をしているので、梅林の中でも他と違った雰囲気がある。大輪で、輪郭がくっきりしていて、しっかりした感じがする。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/800秒 70mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
22.思いのまま -3
最初の梅林の先を廻って、二つ目の梅林を見てきたが、一回りして最初の梅林の入り口へ戻ってきた。「思いのまま」をもう一度獲る。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
23.釣りを楽しむ人たち
2mほどの間隔を空けて数人の釣り人が楽しんでおられtら。大池には大きな鯉が泳いでいたが、何が釣れるのだろうか?
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 50mm ISO110 ) 露出補正 なし
|

|
24.弁財天
大池の池端に弁財天の石洞が祀られており、寛政2年(1790年)2月に建立と刻まれているが、天明2年(1783年)の大飢饉で大勢の人々が亡くなったことを供養して建てられたと伝えられているそうだ。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 50mm ISO110 ) 露出補正 なし
|

|
25.池端の乙女
弁財天に近いところの池端に「井上〇道」と銘の入った「池端の乙女」と題された乙女の像がある。〇のところは擦れてしまっていて読み取れなかった。ネットで検索してみたところ、1975年に横浜文化賞を受賞し、2008年に99歳で亡くなられた彫刻家井上信道さんと思われる。
Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/500秒 35mm ISO110 ) 露出補正 なし
|