昆虫切手研究会のSさんから、足立区生物園で保全のための飼育をしているツシマウラボシシジミを9/18から同23まで大温室に放蝶、公開するというお知らせをいただいた。足立区生物園ではツシマウラボシシジミの絶滅を防ぐため、生息域外保全の活動を行なっている。大温室の一部区画にて本種の交配を行ない、交配済みの 成虫から採卵する。孵化した幼虫は個別に飼育管理し次世代へと繋ぐ活動をされている。生物園では本種の個体数を安定させ、生息地の対馬へ戻すことを目標にしている。
wikipediaには1969年に「ツシマウラボシシジミ繁殖地」が上県町(対馬の北部西岸の町)の天然記念物となり、2005年の市町村合併により対馬市の天然記念物に指定された。その後、急激なシカの増加に伴う林床植生の食害およびこれに伴う林内の乾燥化で、本種の好む林床植生が破壊され、幼虫の食草であるヌスビトハギ類や成虫の吸蜜植物が激減し、2013年にはほぼ野生絶滅の状態にまで陥った[3]。2017年には環境省の「種の保存法」の国内希少野生動植物種に指定された。と記されている。先日も舞岡公園でヌスビトハギを見たが、恥ずかしながら、そのときはツシマウラボシシジミの食草であるとは知らなかった。
私は足立区生物園には過去3回訪れている。2015年2月に西新井大師のお参りを兼ねて、初めて行った。2回目は2016年のGWに日本チョウ類保存協会からのお知らせで知って放蝶されたツシマウラボシシジミを見に行った。3回目は2018年の2月で、新しく購入したカメラである SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ の蝶撮りを試しに行き、今回が4度目である。
いつもはマイカーで行くのだが、この日初めて電車を利用した。地下鉄日比谷線に乗って竹ノ塚迄行き、駅からタクシーで750円の距離だった。だが、2時間たっぷりかかってしまった。8時15分ごろ家を出て、撮影を始めたのは10時半だった。
期間中、毎日8~10頭程度で放蝶されるのはすべて 。放蝶された個体は夕方には回収される( は産卵の問題があり、放蝶出来ないそうだ)。保全活動にご尽力されている方々のご苦労には申し訳ないが、残念ながら放蝶されていた個体は、擦れていて、鱗粉の脱落、また、個体識別のためのマーキングがなされていた。
この日は正午ごろまで撮影した。

|
1.ツシマウラボシシジミ -1
10時半過ぎに温室の中に入った。クロテンシロチョウが迎えてくれた。まずは、何が翔んでいるか温室の中を見回す。さっそく、1頭の小さなチョウを見つけた。足立区生物園のHPによれば、この日、ツシマウラボシシジミは8頭が放蝶されているようだ。クサギのような花に止まっている。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 1400 ) 露出補正 なし
|

|
2.ツシマウラボシシジミ -2
最初の写真とは別のの個体である。後翅裏面に茶色の個体識別のマーキングがされている。裏面外縁の薄茶色の縁取りは薄れてしまっていた。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 280 ) 露出補正 なし
|

|
3.ツシマウラボシシジミ -3
また別の個体のようだ。xの識別マークが付けられている。紫色のタイワンレンギョウの花にストローを伸ばしている。ツシマウラボシシジミは、日本国外ではインド北東部のアッサム地方やミャンマー、ベトナム、中国、台湾に分布する。日本では対馬にのみ生息する。環境省レッドリストの絶滅危惧ⅠA類および、「種の保存法」における国内希少野生動植物種に指定されている種である。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 900 ) 露出補正 なし
|

|
4.ヒギリ(緋桐)の花に来たクロアゲハ -1
温室にある大きなヒギリ(シソ科の低木)の木がいっぱい花を咲かせているが、そこに黒いアゲハたちが飛来する。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 560 ) 露出補正 なし
|

|
5.カバタテハ -1
カバタテハは、日本では以前は迷チョウであった。1967年に石垣島と西表島、1973年に西表島で記録された。1980年から波照間島や竹富島で継続的に見られるようになった。八重山のほぼ全域に生息していたが最近では、あまり見られないそうだ。私は2005年5月に竹富島で撮影している。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 720 ) 露出補正 なし
|

|
6.リュウキュウアサギマダラ
デュランタ(タイワンレンギョウ)の花で2頭のリュウキュウアサギマダラが吸蜜。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 560 ) 露出補正 なし
|

|
7.ツシマウラボシシジミ 飛翔
ツシマウラボシシジミは止まるときは翅を閉じている。表側を撮るには翔んでいるところを狙うしかない。このショットはホナガソウ (穂長草)に絡んでいるところを撮ったが、多少被写体ブレはしているものの、翅表の黒褐色に縁取られた金属光沢のある青藍色を見せてくれた。 の表面は一様に黒褐色である。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 2200 ) 露出補正 なし
|

|
8.カバタテハ -2
カバタテハは比較的破損の無いきれいな個体が多かった。 だと思う。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 500 ) 露出補正 なし
|

|
9.ツシマウラボシシジミ -4
ホナガソウに逆さまに止まって吸蜜している。絞り優先オートで撮る。最低シャッタースピード1/500秒でISO100より暗くなると、ISO感度で露光をコントロールしている。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 900 ) 露出補正 なし
|

|
10.アサギマダラとヒメアサギマダラ
ランタナ(和名はシチヘンゲ 七変化)の黄色い花で吸蜜するアサギマダラにヒメアサギマダラが絡んできた。アサギマダラの後翅には "9・14" というマーキングがされていた。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 900 ) 露出補正 なし
|

|
11.ツマグロヒョウモン
横浜でもお馴染みのチョウである。きれいな個体だったので撮った。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 180 ) 露出補正 なし
|

|
12.イシガキチョウ -1
他の種には見られない特異な模様の衣装をまとっている。よく見ると尾状突起が付いている。多化性で、成虫は越冬を終えた春から発生を繰り返し、秋遅くまで見られる。食樹はクワ科のイヌビワ・イチジク・オオイタビなど。温暖化により北上している蝶のひとつでもあり、国内では年々分布域を広げている。確実に土着しているのは紀伊半島以南・四国・九州・南西諸島である。四国に旅行した時、高知でレストランの看板に止まる本種を見て、驚いたのを覚えている。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 105mm ISO 100 ) 露出補正 なし
|

|
13.ツシマウラボシシジミ -5
これは比較的擦れていないきれいな個体だった。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 320 ) 露出補正 なし
|

|
14.ツシマウラボシシジミ
ホソバソウの花に着地し、止まって翅を閉じる直前の姿だ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 200 ) 露出補正 なし
|

|
15.ツシマウラボシシジミ -7
写真13~15は同じ個体のようだ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 140 ) 露出補正 なし
|

|
16.イシガキチョウ -2
本種が止まるときは、ほとんどこのように翅を開いている。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/1000秒 105mm ISO 1400 ) 露出補正 なし
|

|
17.ジャコウアゲハ -1
ホナガソウはチョウたちの好きな花のようだ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/1000秒 105mm ISO 200 ) 露出補正 なし
|

|
18.ジャコウアゲハ -2
前の写真と同じ個体。後翅尾状突起のあたりの赤い紋がはっきりしている。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 180 ) 露出補正 なし
|

|
19.ヒギリの花に来たクロアゲハ -2
この花に止まるとクロアゲハも小さく見える。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/500秒 105mm ISO 200 ) 露出補正 なし
|

|
20.クロテンシロチョウ
ゆっくりと翔ぶのだが、方向定まらず翔んでいるところは撮れなかった。以前は台湾などからの迷蝶だったが、1980年代の終わりから与那国島、波照間島、西表島、石垣島と分布をゆっくり広げているという。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 105mm ISO 100 ) 露出補正 なし
|

|
21.ツマムラサキマダラ -1
ツマムラサキマダラも以前は国内には定着しておらず、迷チョウとして扱われていたが、1992年頃から沖縄島に定着し、現在では奄美から八重山諸島にかけて分布が確認されている。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 105mm ISO 400 ) 露出補正 なし
|

|
22.ツマムラサキマダラ -2
♂は前翅が紫青色に輝くが、 ♀はその輝きは鈍い。後翅の斑紋は雌雄で異なる。比較的きれいな個体だった。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 105mm ISO 280 ) 露出補正 なし
|

|
23.ヒギリの花に来たオキナワカラスアゲハ
本土にいるカラスアゲハやミヤマカラスアゲハに比べ、後翅の青の輝きが特徴的で、一見して識別できる。この個体はその後翅の破損が大きく残念だ。美麗な蝶と思う。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 105mm ISO 250 ) 露出補正 なし
|

|
24.ツシマウラボシシジミとアサギマダラ -1
タイワンレンギョウの花に、マーキングされたツシマウラボシシジミと、マーキングされたアサギマダラが吸蜜していた。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 105mm ISO 1000 ) 露出補正 なし
|

|
25.ツシマウラボシシジミとアサギマダラ -2
両者はさらに近づいた。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 105mm ISO 360 ) 露出補正 なし
|

|
26.ヒギリの花にクロアゲハとオキナワカラスアゲハ
破損ができるだけ目立たないように撮る。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 105mm ISO 1000 ) 露出補正 なし
|

|
27.カバタテハ -3
取り分けてきれいな個体だったので撮った。温室内で羽化しているのだろうか。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 105mm ISO 1000 ) 露出補正 なし
|

|
28.スジグロカバマダラ
見栄えのするチョウである。 は後翅に性標がるのが、この写真ではよくわからない。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 105mm ISO 280 ) 露出補正 なし
|

|
29.リュウキュウヒメジャノメ
石垣島では林道などでよく見たチョウである。関東で見るヒメジャノメやコジャノメに比べ裏面前翅から後翅にかけての白い帯が目立つ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 105mm ISO 1250 ) 露出補正 なし
|

|
30.ヒメアサギマダラ
本種もかっては迷チョウであったが、1980年代後半から与那国島で継続的に発生するようになった。八重山諸島各地で記録されている。今回はツマベニチョウやコノハチョウに会えなかったのは残念だった。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S
絞り優先優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 105mm ISO 560 ) 露出補正 なし
|




























































































































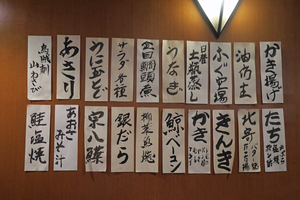







































 足立区生物園入り口
足立区生物園入り口
































































