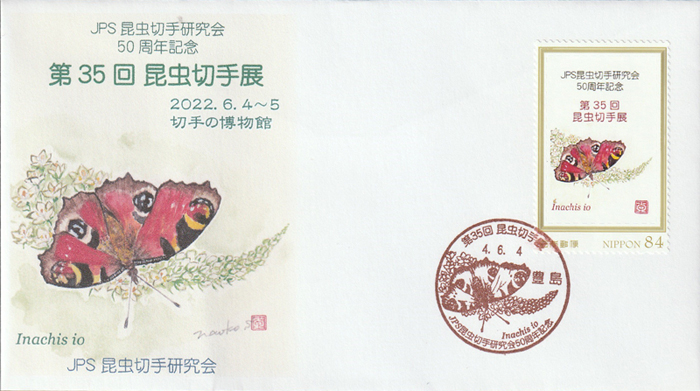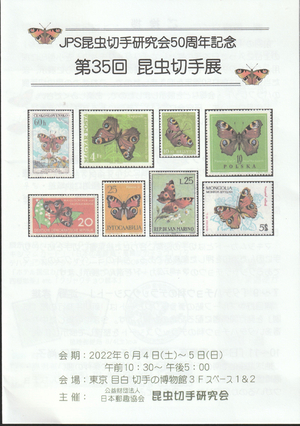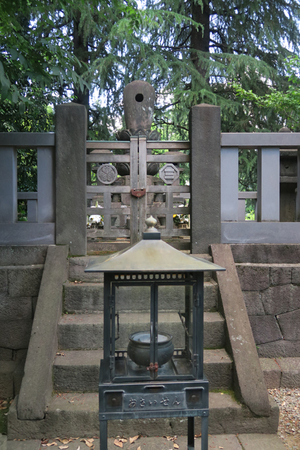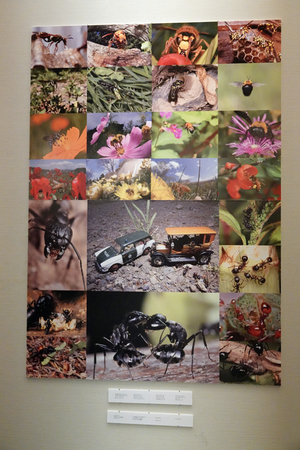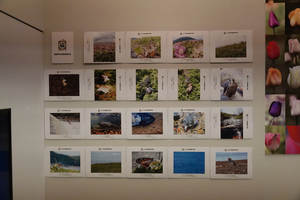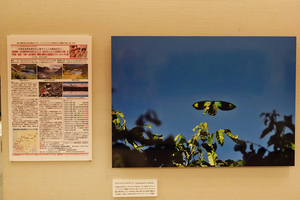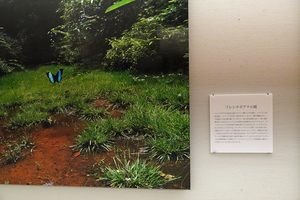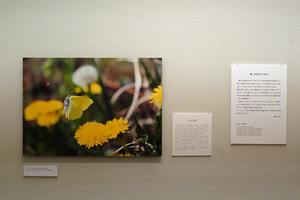私が初めて、いま世界的パンデミックとなっている新型コロナウィルス肺炎のことを意識し始めたのは、湖北省武漢市で昨年(令和元年)12月以降(実際は11月から始まっていた)、新型コロナウイルス肺炎の発生が報告され、日本をはじめとして世界各地からも報告がなされるようになった今年の1月中頃だった。
そして、4月2日現在の感染者数は アメリカ 203,608人、イタリア 110,574人、 スペイン 102,136人、中國 801,554人、日本は検査数の問題はあるが 2,510人、全世界では 827,419人である。亡くなられた方の数は イタリア 13,155人、スペイン 9,053人、アメリカ 4,476人、中國 3,312人、日本 81人、世界で 40,777人に達している。日本はまだ、感染者数の多寡はともかくとして、死亡者はオーダーが違うほど少ない。
しかし、3月の終わりごろから、日ごとの感染者数の増加は増えてきている。このまま増え続けると医療崩壊を起こしかねない状況となってきた。不要不急の外出自粛が要請されている。
チョウの写真を撮りにフィールドへ出ることも、感染の心配はほとんどないと思うが、後ろ髪をひかれる思いがする。4月に入って、ようやく昨日今日と日差しが戻り、気温も上がり、ギフチョウの撮影には絶好であるが断念した。これからしばらくは動きにくくなる。
ブログに載せる写真も撮れないので、ディスクにストックしてある昔の写真を頼りに、ここらで、私が舞岡公園で、過去17年間に撮影したチョウの写真を種別にまとめておこうかという気になった。
私が舞岡公園のことを知ったのは、「相模の蝶を語る会」の企画・編集で神奈川新聞社が発行・制作した「かながわの蝶-バタフライウォッチング-」だった。この約170ページの冊子は2000年5月1日に初版が発行されている。
舞岡公園を初めて訪れたのは、2003年6月7日だった。平地産のゼフィルスに会いたいと思ったからだ。「かながわの蝶-バタフライウォッチング-」では、舞岡公園には、ミドリシジミ、オオミドリシジミ、アカシジミ、ウラナミアカシジミ、ミズイロオナガシジミ、ウラゴマダラシジミの6種の平地産ゼフィルスが生息するとされていたが、初めて訪れた舞岡公園では出会うことはなかった。
私は2003年9月に川崎市中原区から横浜市保土ヶ谷区に転居した。翌2004年には横浜市緑区の十日市場の近くの新治町の谷戸である新治市民の森へも行った。最初に平地産ゼフィルスを撮ったのはここで、オオミドリシジミとミズイロオナガシジミだった。しかし平地産ゼフィルス以外の蝶相は舞岡公園のほうが豊かで、春から秋にかけて撮影を楽しむようになり、2003年から足掛け17年、舞岡公園へ通うことになったのだ。
舞岡公園のことはインタネットでも情報が得られた。多分お近くにお住まいの higirinikki というかたの「舞岡公園の自然」はほぼ毎日更新され、蝶のことはもちろん、他の昆虫や、鳥、草花や環境について写真と解説が掲載されている、2005年9月に開設されたこのブログは2015年2015年10月には述べ閲覧回数が55万回に達し、「舞岡公園の自然 2」に受け継がれている。蝶の発生状況や、蝶が吸蜜する草花についても参考にさせていただくことは多大である。
もうひとつ「暖蝶寒鳥」というブログを見つけた。オーナーは横浜市の金沢区にお住まいだったが、2018年11月に札幌に移住された。舞岡公園では、私もまだ見ることが出来ないでいるオナガアゲハ(2014年8月撮影)、ミヤマカラスアゲハ(2009年9月撮影)の写真も撮られてアップされている。札幌に移られてからも「暖蝶寒鳥」は続けられており、素晴らしい野鳥の写真をはじめ、北海道の自然を楽しみに見せていただいている。
さて、私のことになるが、2003年に初めて舞岡公園を訪れて以来、足掛け17年、もちろん、毎日というわけにはいかず、平地産ゼフィルスの発生時期を中心に年に10回行くか行かないかというところだが、これまでに舞岡公園に生息する55種のチョウの写真を撮ってきた。「暖蝶寒鳥」で写真が掲載されていたオナガアゲハ、ミヤマカラスアゲハに加え、いると聞き及んでいるヒオドシチョウ、ゴイシシジミはまだ撮っていない。 アゲハチョウ科からセセリチョウ科まで、少々時間はかかると思うが何回にも分けてアップしていこうと思っている。なお、すでにStudio YAMAKOで使用した写真からも抜粋し再掲している。 分類は日本チョウ類保全協会編の「フィールドガイド 日本のチョウ」に準じた。
1.アゲハチョウ科 ① クロアゲハ、ナガサキアゲハ、モンキアゲハ
01) クロアゲハ
10101 2005年6月24日 撮影
羽化したばかりのような美しい♂だった。
撮影データ不詳
|

|
10102 2005年9月12日 撮影
ヤブガラシで吸蜜する♀
データ不詳
|

|
10103 2009年7月19日 撮影
ヤブガラシに飛来した♂
Nikon D300 Tokina 100mm f2.8 macro
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/640秒 100mm ISO400 ) 露出補正 -0.3段
|

|
10104 2009年8月19日 撮影
クロアゲハはヤブガラシが好きだ。
Nikon D300 SIGMA 70-300mm apo macro f4.5-5.6
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 300mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段
|

|
10105 2019年6月13日 撮影
このころ、クロアゲハはよく路の水たまりで吸水している。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 117mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
10106 2019年6月18日 撮影
ミドリシジミの♀を撮ろうと出かけると、よくこういう光景が見られる。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 31mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
02) ナガサキアゲハ
10201 2007年9月4日 撮影
静止しているのではなく、翔んでいたところを捉えた。
Nikon D100 NIKKOR 18-200mm f3.5-5.6G
プログラムオートで撮影 ( F9 1/1250秒 ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
10202 2010年5月15日 撮影
春、タニウツギの花に飛来
Nikon D5000 SIGMA 17mm-70mm f2.8-4.5G
プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/250秒 70mm ISO400 ) 露出補正 -0.3段
|

|
10203 2010年5月15日 撮影
♂ 比較的破損していない。
Nikon D5000 SIGMA 17mm-70mm f2.8-4.5G
プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1600秒 70mm ISO400 ) 露出補正 -0.3段
|

|
10204 2012年10月5日 撮影
農家の花壇の花で吸蜜。ナガサキアゲハは♂♀ともまだ、新鮮な個体が撮れないでいる。
Nikon D300 Tokina 100mm f2.8 macro
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1000秒 100mm ISO400 ) 露出補正 -0.3段
|

|
03) モンキアゲハ
10301 2003年6月7日 撮影
初めて舞岡公園を訪れたときに撮った。
Nikon COOLPIX S10 f3.5 6.3-63mm 6.0 Mega Pixels
撮影データ不詳
|

|
10302 2006年9月4日撮影
♀は時々このように、葉っぱの上に翅を開いて止まる。
Nikon D100 Tokina 100mm f2.8D macro
プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/60秒 ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
10303 2008年9月3日 撮影
クサギに飛来した♂
Nikon D300 Tokina 100mm f2.8D macro
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/800秒 100mm ISO400 ) 露出補正 なし
|

|
10304 2008年9月3日 撮影
♂ 夏の終わり、モンキアゲハはクサギの花が好きだ。
Nikon D300 Tokina 100mm f2.8D macro
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/800秒 100mm ISO400 ) 露出補正 なし
|

|
10305 2009年8月19日 撮影
新鮮なモンキアゲハ♂と、擦れてしまったカラスアゲハ♂
Nikon D300 SIGMA 70-300mm apo macro f4.5-5.6
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/400秒 300mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段
|

|
10306 2009年8月19日 撮影
クサギの花が咲くところで舞っていると、次々とモンキアゲハがやってくる。
Nikon D300 SIGMA 70-300mm apo macro f4.5-5.6
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/2500秒 300mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段
|

|
10307 2009年8月19日 撮影
モンキアゲハ♂ 花から離脱
Nikon D300 SIGMA 70-300mm apo macro f4.5-5.6
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/2500秒 300mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段
|

|
10308 2010年5月15日 撮影
タニウツギを訪れた♂
Nikon D5000 SIGMA 17mm-70mm f2.8-4.5G
プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 70mm ISO400 ) 露出補正 なし
|

|
10309 2010年5月15日 撮影
春はもっぱらタニウツギ
Nikon D5000 SIGMA 17mm-70mm f2.8-4.5G
プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 70mm ISO400 ) 露出補正 なし
|

|
10310 2010年5月15日 撮影
タニウツギの花を離れる♂
Nikon D5000 SIGMA 17mm-70mm f2.8-4.5G
プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/640秒 70mm ISO400 ) 露出補正 なし
|

|
10311 2010年5月15日 撮影
花から花へ 楽しそうだ。
Nikon D5000 SIGMA 17mm-70mm f2.8-4.5G
プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 70mm ISO400 ) 露出補正 なし
|

|
10312 2010年8月14日 撮影
この個体は少し擦れている。
Nikon D5000 NIKKOR 18-200mm f3.5-5.6G
プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/320秒 200mm ISO400 ) 露出補正 なし
|

|
10313 2012年8月30日 撮影
♂
開翅
Nikon D300 SIGMA 70-300mm apo macro f4.5-5.6
絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/640秒 300mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段
|

|
10314 2012年8月30日 撮影
クサギの花から離脱
Nikon D300 SIGMA 70-300mm apo macro f4.5-5.6
絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/1600秒 300mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段
|

|
10315 2012年8月30日 撮影
ホバリングして吸蜜
Nikon D300 SIGMA 70-300mm apo macro f4.5-5.6
絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/2500秒 300mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段
|

|
10316 2012年8月30日 撮影
小刻みに翅を打ちながら吸蜜する。
Nikon D300 SIGMA 70-300mm apo macro f4.5-5.6
絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/24000秒 300mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段
|

|
10317 2015年5月3日 撮影
このタニウツギは剪定されて、次の年には花が咲かなくなってしまった。
Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f5.5 1/100秒 54mm ISO400 ) 露出補正 -0.3段
|

|