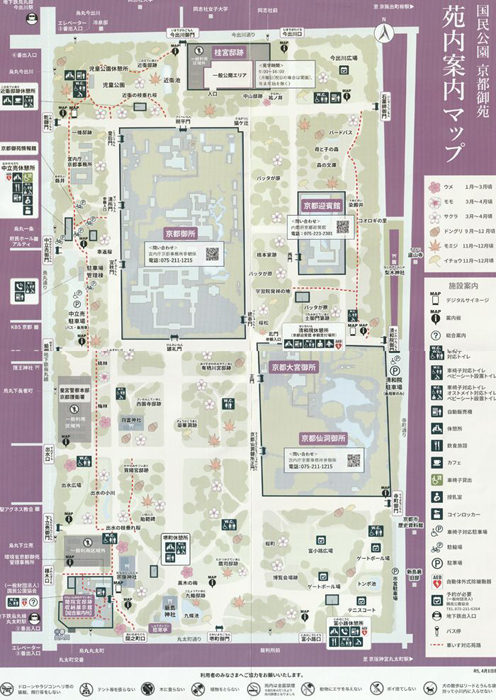西新井大師は、足立区生物園からは車で15分くらいだったろうか。足立区生物園もそうだったが、西新井大師にも自家用車用の駐車場はなく、近くの有料駐車場に車を停めて、境内に入った。
停めた駐車場からは西新井大師の裏側から境内に入ることになる。總持寺と書かれたた大きな建物は大本堂だった。その左側から出生稲荷という稲荷社の脇を通って表側に回る。香炉から振り返って大本堂を仰ぎ、参拝した。
そこから、山門を抜けて参道を歩く。平日の午後、参拝者は多くなく、参道に並ぶ店にもいまひとつ活気がない。
どこで昼食にしようかと思ったが、山門の前の左側に、店先で元気のいいおばさんが草団子を売っている「清水屋」さんという食堂があった。ショウ・ケースにあった蕎麦でも頼もうと思っていたが、店の中に入ると立派な鮨のカウンターがあり、板さんが握っていた。案内されたテーブルの隣の席の夫婦が食べている鮨が旨そうだったので、上鮨を食べることにした。腹も減っていたが、味もまずまずだった。
食事を終え、再び山門から境内に入り、本堂の両脇にある梅と寒桜を見た。寒桜にメジロが来ていてかわいい。
帰路も首都高で順調に帰ってきたが、首都高で流れに乗って走ると80km/hになってしまう。
13.出世稲荷明神
大本堂の裏側から入り、左手に回っていくと、この出世稲荷明神があった。立てられている札には、本来五穀の神である倉稲魂神(うかのみたま)を祭ったものであり、弘法大師が嵯峨天皇より東寺を賜った時に、明神が翁の姿となって現れ、救いを垂れられたので、当時の鎮守として祭られ盛んになったといわれると書かれていた。ちょっと意味が良くわからない。出世という言葉はもともと仏教用語で、「悩みや迷いから離れ、世俗を超越」することを言うようだとのこと。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/800秒 27mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
14.大本堂
西新井大師のホーム・ページによれば、西新井大師は五智山遍照院總持寺(ごちさん へんじょういん そうじじ)といい、真言宗豊山派の寺院である。天長(824年~834年)の昔、弘法大師が関東巡錫(じゅんしゃく )の折、当所に立ち寄り悪疫流行に悩む村人たちを救わんと、自ら十一面観音像とご自身の像をお彫りになり、観音像を本尊にそしてご自身の像を枯れ井戸に安置して21日間護摩祈願を行ったところ、清らかな水が湧き、病はたちどころに平癒したと伝えらえる。その井戸がお堂の西側にあったことから「西新井」の地名ができたとう。この大本堂は昭和47年に落慶し、ご本尊 十一面観音と弘法大師を祀っている。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1000秒 20mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
15.大本堂の扁額
大本堂の扁額は遍照殿と記されている。あまなく照らすという意味だそうだ。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 28mm ISO560 ) 露出補正 なし
|

|
16.さびしいお面屋さん
西新井大師は牡丹が有名である。牡丹は昔、奈良の真言宗豊山派の総本山である長谷寺から移植され、西新井大師では文化・文政(1804年-1830年)の頃よりぼたん園が展開されたという。ぼたん園は3つあり、その入り口にはこのような店が出ている。今は牡丹の咲く季節ではない。今日は参拝者も少なく、さびしい。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1000秒 62mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
17.水屋
山門を背に境内の参道の右手に水屋がある。詳しいことはわからないが手水鉢の四隅を支える像が良い。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 24mm ISO320 ) 露出補正 なし
|

|
18.山門
境内から山門を見る。山門は江戸時代後期の建立だそうだ。素木造、楼上に五智如来を安置し両脇に寺門安護の金剛力士像をまつる。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 18mm ISO1000 ) 露出補正 なし
|

|
19.山門の金剛力士像
これは向かって右側の金剛力士像。このように手前に金網がある被写体はオート・フォーカスは苦手である。もちろん左側にもう一体ある。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 18mm ISO2000 ) 露出補正 なし
|

|
20.表参道からの山門
左側にある店が昼食をした「清水屋」さん。正面に大本堂が見える。扁額には五智山とある。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 18mm ISO2000 ) 露出補正 なし
|

|
21.参道の街並み
参道には両側に店が立ち並ぶが、ちょっと古めかしい店もある。手前が時計屋さんで、奥はせんべい屋さん。時計屋さんは「竹内時計店」といい、Yahoo智慧袋に、アンティーク時計の修理など、知る人ぞ知る名物職人の店主さんが居るお店と紹介され、「先代の店主である現店主のお父さんが名工で、現主人はその魂を引き継ぎ、更に素晴しい仕事をされております。」という書き込みを見つけた。TVのアド街ック天国にも登場している。奥のせんべい屋さんは「浅香家」で、あるブログに「この界隈は他にもせんべい屋はたくさんありますが、なかでも威風堂々(旧態依然)としているのがこの店で、オススメは馬目焼きという超弩級堅焼きせんべい。これはナント1枚200円もするのですが、これを一度食べると、他のせんべいが物足りなります。ガッシリ分厚くて堅くて味が深くて旨いのです。厚さ、堅さ、せんべい本体と醤油の味のバランスが素晴らしい。」と紹介されていた。この日は閑散としていた。知っていたら買って帰ったのだが。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 32mm ISO360 ) 露出補正 なし
|

|
22.光明殿の屋根
山門の前で右手を見ると、大きな、立派な屋根が見えたので行ってみる。そこには法事等仏事が行われる光明殿があった。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/640秒 20mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
23.光明殿八角堂
その奥に八角堂があった。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1000秒 35mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
24.境内に咲く梅
再び境内に戻る。食事をした「清水屋」さんで、「梅はあるのですか?」と聞いたところ、大本堂の両側にあると教えていただいた。さっそく、大本堂の右手へ行ってみると、紅梅が咲き始めていた。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/320秒 122mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
25.三匝堂(さざえ堂)
今度は大本堂の左側に回った。境内の一角にさざえ堂がある。正式には三匝堂(さんそうどう)と呼ばれるが、見た感じは普通の三重塔とさほど変わりない。三匝堂という形式は江戸時代に流行し、関東以北には相当建てられたそうだが、今に残る遺構は大変珍しく、都内では明治17年に改築されたこの堂のみだそうだ。三重塔との決定的な違いは、内部に入り一階から三階までに安置されている無数の仏像群を、順に参拝できるようになっているということだそうだ。ただし現在では、階段も外され、内部に入ることすらできないとのこと。 一匝に八十八体大師像、二匝に十三佛、三匝に五智如来と二十五菩薩が祀られている。匝という字は難しいが、音読みで「ソウ」、訓読みで「めぐる」と読む。意味はめぐる。周囲をまわる。取り巻く。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 18mm ISO450 ) 露出補正 なし
|

|
26.寒桜
大本堂の左手には、梅もあったが、寒桜があった。立てられている札には、(珍樹)寒桜とあり、「当山のこの桜はカンヒザクラ系の雑種で、桜の中では最も早く開花し、通常であれば二月上旬から三月上旬ごろまで長期間楽しむことができる。このような寒桜は都内ではあまり見ること出来ない。」と説明されていた。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/800秒 75mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
27.咲きはじめの寒桜
びっしりと蕾を付け、その中の数輪が花開いていた。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/800秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
28.寒桜にめじろ
メジロがやってきて、寒桜の蕾を啄む。かわいらしい。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/800秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
29.奥ノ院
高野山の奥の院を江戸後期に関東に奉迎し、この地に弘法大師を祀る。古くから「関東の高野山」とも呼ばれていたそうだ。
Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/250秒 30mm ISO560 ) 露出補正 なし
|

|