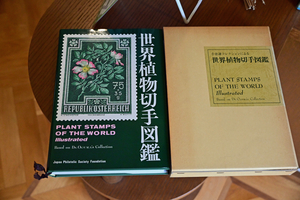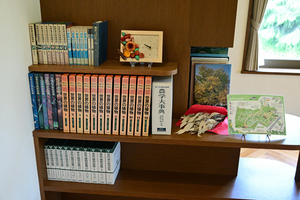初めて入笠山へ行ったのは、ちょうど延長2,489mのゴンドラが完成した1992年だった。だが、そのゴンドラは、いわば最長滑走距離が3,000mという大きなスキー・ゲレンデの山頂駅(1,780m)に上がるためのもので、夏の入笠山登山を目的としたものではなかったようだ。
その山頂駅周辺は現在はマイカーで立ち入ることはできないが、初めての入笠山へ行ったときは、その麓の花畑までマイカーで入れた。そのころの撮影地は、大阿原湿原、入笠山花畑、入笠牧場、鐘打平のあたりだった。その後、夏季シーズンの車両進入は規制されている。
初めてゴンドラに乗って入笠山に入ったのは、2020年8月4日だった。この時初めて「入笠すずらん山野草公園」を知った。
今回は朝6時にマイカーで自宅を出発し、途中休みながら、8時45分にゴンドラの乗り場に到着した。たっぷり4時間撮影を楽しみ、2時過ぎのゴンドラで下り、一休みして、午後3時に帰路に着いた。

|
1.ゴンドラすずらん
ゴンドラはまだ空いていた。往復料金は2千円。標高1,780mまで標高差730mを運んでくれるのだから、その値打ちはあると思う。ちなみに中央高速道の最高標高地点は富士見町(小淵沢と諏訪南の間)の1,015mだそうだ。ゴンドラは緩やかな登りから急斜面の登りになる。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/400秒 23mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
2.ゴンドラ山頂駅付近
9時30分にゴンドラの山頂駅に着いた。右下に八ヶ岳連峰を背景にして写真をとる枠が見えるが、そこには愛犬を連れた家族連れが来ていた。ここはリードさえ付けていれば、愛犬をゴンドラにも乗せられるし、飼い主と一緒に高原を歩かせることもできる。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 19mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
3.ウラナミシジミ
「入笠すずらん山野草公園」に入る前に、少し入笠湿原の方に歩いてみた。ノアザミに何かシジミチョウが止まっている。意外にもウラナミシジミだった。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.2 1/1000秒 105mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
4.マツムシソウ(松虫草)とクジャクチョウ -1
マツムシソウが咲いていた。何かいないかと探していると、クジャクチョウが吸蜜していた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4,0 1250秒 203mm ISO320 ) 露出補正 なし
|

|
5.エゾカワラナデシコ(蝦夷河原撫子) -1
入笠山は花が多い。今回は花の写真も撮っておきたいと思う。この花は種子には薬効があり、カワラナデシコと同様に消炎、利尿、通経作用があるそうだ。カワラナデシコは苞が3~4対あり。このエゾカワラナデシコは2対だ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.0 1/1000秒 105mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
6.マツムシソウとクジャクチョウ -2
クジャクチョウの裏面は真っ黒で、僅かに複雑な縞模様がある。日に照らされて透き通って、表の模様が見える。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4,0 1250秒 200mm ISO640 ) 露出補正 なし
|

|
7.マツムシソウとクジャクチョウ -3 離脱
吸蜜していたマツムシソウの花から離脱した。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4,0 1250秒 207mm ISO250 ) 露出補正 なし
|

|
8.地面に止まるクジャクチョウ -1
クジャクチョウやキベリタテハなどは、良く地面に静止する。その時はほとんどの場合開翅している。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.0 1/1000秒 105mm ISO110 ) 露出補正 なし
|

|
9.マツムシソウとクジャクチョウ -4
ほとんど傷のない美しいクジャクチョウばかりである。第2化の最盛期なのだろう。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4,0 1250秒 220mm ISO1000 ) 露出補正 なし
|

|
10.マツムシソウとクジャクチョウ -5
こんなに多くのクジャクチョウを見るのは久しぶりである。中学生のころ、美ヶ原の麓の三城牧場で、何の花だったか忘れてしまったが、その花が真っ黒に見えるほど多くのクジャクチョウが止まって吸蜜していたのを思い出した。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4,0 1250秒 207mm ISO640 ) 露出補正 なし
|

|
11.エゾカワラナデシコ -2
可憐な花である。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4,0 1250秒 220mm ISO250 ) 露出補正 なし
|

|
12.マツムシソウとクジャクチョウ -6
今咲いている花の中ではマツムシソウが一番のお気に入りのようだ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 105mm ISO180 ) 露出補正 なし
|

|
13.ハーベストベルズ
「入笠すずらん山野草公園」を歩き始めた。まだ、散策する人は多くない。これは私のような花の素人には、リンドウ(竜胆)としか思えないが、念のためPictureThisで検索してみると、ハーベストベルズと同定された。山で見かけるリンドウは国内では複数の種類が自生しているという。ゴンドラの切符売り場で渡された小冊子には、エゾリンドウとしか載っていなかった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4,0 1250秒 208mm ISO250 ) 露出補正 なし
|

|
14.アキノキリンソウ(秋の麒麟草)
高さは70〜80cm程度となり、8〜11月に総状(ふさのような形をしている)の黄色い花を多数つける。山地や丘陵の日当たりのよい場所に生える。箱根の湿性花園や、先日行った上高地では見ているが、平地では見たことがない。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4,0 1250秒 132mm ISO250 ) 露出補正 なし
|

|
15.ツリガネニンジン(釣鐘人参)
ツリガネニンジンという和名の由来は、花が釣鐘形で、根の形がチョウセンニンジンに似るのでこの名があるという。山野、山麓、山地の草原、林縁、草刈などの管理された河川堤防などに自生する種で、都会では見たことがない。花冠から突出する花柱が鈴を叩く棒のようで、印象的だ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/1000秒 105mm ISO180 ) 露出補正 なし
|

|
16.コマツヨイグサ(小待宵草)
ゲレンデの土に生えていた。北アメリカ原産で、アジアやアフリカに帰化植物として移入分布している。日本では本州・四国・九州に広く定着している。日本では1910年代に初めて確認されたそうだが、在来種と競合し、在来種の数を大きく減らし、生態系を崩す事から外来生物法により要注意外来生物に指定されているそうだ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 105mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
17.ウラギンヒョウモン♀
ヤマハハコの花で吸蜜していた。ウラギンヒョウモンとギンボシヒョウモンは翅表では区別が付けにくい。これは♀であるが、ウラギンヒョウモンの方がやや大型で、斑紋の黒が際立つ。きれいな個体だった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4,0 1250秒 216mm ISO400 ) 露出補正 なし
|

|
18.ゼラニウム・シルバティカム -1
フウロの一種と思ったが、PictureThisで検索すると、ゼラニウム・シルバティカスと出た。フウロソウ科 フウロソウ属ではある。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4,0 1250秒 55mm ISO800 ) 露出補正 なし
|

|
19.コヨメナ(小嫁菜)
PictureThisで検索して、コヨメナと同定された。wikipediaによれば、コヨメナは道端で見かける野菊の一種である。南方から侵入したと考えられるそうだ。秋に自宅近くの帷子川に沿って歩くと、コヨメナにヤマトシジミが絡んでいる。ただ、コヨメナによく似た花にヨメナをはじめ、ノコンギクやシロヨメナがあり、花だけ見たのではちょっと区別がつかないそうだ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.2 1/1000秒 105mm ISO360 ) 露出補正 なし
|

|
20.レンゲショウマ(蓮華升麻) -1
花が蓮華に、葉がサラシナショウマ(晒菜升麻)に似ているので、レンゲショウマ(蓮華升麻)の名がつけられたそうだ。薄紫の上品で気品あふれる花が、下を向いて咲いていた。箱根湿性花園にも咲いている。また、近郊では奥多摩の御岳山が有名である。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.4 1250秒 9mm ISO400 ) 露出補正 なし
|

|
21.ゼラニウム・シルバティカム -2
これはハクサンフウロかなと思って撮影したが、PictureThisで検索すると、やはりゼラニウム・シルバティカスと回答された。花びらの先端が両者で少し違うように見える。なお、wikipediaによれば、フウロソウ属(学名 Geranium)は、フウロソウ科に分類される多年生草本植物の属の名称で、420種以上が確認されている。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.0 1/1000秒 105mm ISO250 ) 露出補正 なし
|

|
22.フシグロセンノウ(節黒仙翁)
箱根湿性花園でも見ている。しかし、ここでは群落になって、まとまって咲いていた。オレンジ色が際立つ。しかし、この花にチョウが来ているのを見たことがない。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.0 1/1000秒 105mm ISO180 ) 露出補正 なし
|