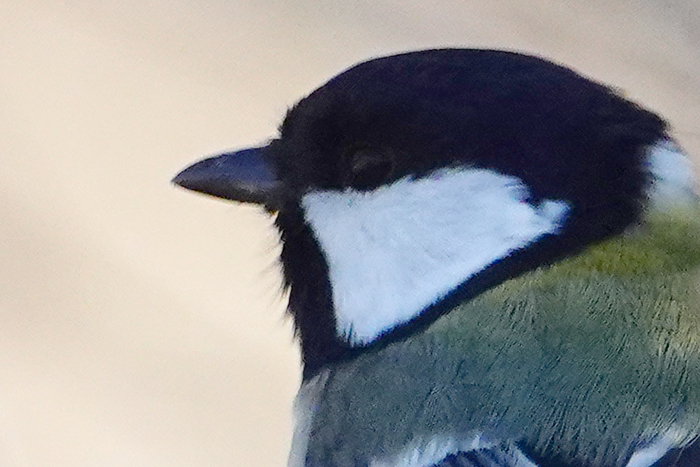|
1.もみじ休憩所
駐車場から南門へ行く前に、まっすぐに進みもみじ休憩所へ寄ってみた。カエデはあまり鮮やかではなかった。夏も赤い葉を付けているノムラモミジもあるが、イロハモミジはまだ紅葉するのにまだ間がある。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 13mm ISO160 )
|

|
2.キタテハ秋型 -1
長久保の池の近くに咲くフジバカマにキタテハ秋型が吸蜜に来ていた。この花もチョウの好きな花である。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO100 )
|

|
3.キタテハ秋型 -2
少し翅が切れているが、まずまずの個体だった。舞岡公園ではフジバカマは咲いているところが少ない。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO250 )
|

|
4.キタテハ秋型 -3
赤褐色が鮮やかだ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO200 )
|

|
5.イソドン(Isodon inflexus)
路傍に咲く小さな花も可憐である。イソドンは在来種で本州、四国、九州に分布し、日当たりの良い場所に生息する多年草の学名だそうだ。シソ科で、和名をヤマハッカ(山薄荷)という。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 136mm ISO1250)
|

|
6.コヨメナ(小嫁菜)
秋にはよく見かける花だ。見た通りのキク科の花で道端で見かける野菊の一種である。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 136mm ISO2000)
|

|
7.ダイコンソウ(大根草)
和名ダイコンソウ は、大根草の意で、根出葉の小葉が大小交互してつくようすが、アブラナ科のダイコン(大根)の葉に似ていることからつけられたという。左上に突き出ているのは、集合果で、花が咲いた後、花柱(めしべの一部分で、柱頭と子房との間の柱状の部分をいい、受精する時は花粉管がこの中をのびる。)の関節の先が脱落し先が曲がった痩果(果皮が堅い膜質で、熟すと乾燥し、一室に1個の種子をもつもの)
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 218mm ISO2500)
|

|
8.トリカブト(鳥兜)
ご存じの鳥兜が咲いていた。トリカブトは、キンポウゲ科トリカブト属の総称だそうだ。山鳥兜、ハナトリカブト、ホソバトリカブトなどがあるようだが、同定はできない。改めてトリカブトの毒性は有名であるが、wikipediaによると「誤食すると嘔吐、呼吸困難、臓器不全、痙攣などによる中毒症状を起こし、心室細動ないし心停止で死に至ることもある。毒は即効性があり、摂取量によっては経口後数十秒で死亡することもある。半数致死量は0.2gから1g。経皮吸収および経粘膜吸収されるため、口に含んだり、素手で触っただけでも中毒に至ることがある。蜜や花粉にも毒性があるため、養蜂家はトリカブトが自生している地域では蜂蜜を採集しないか、開花期を避けるようにしている。また、天然蜂蜜による中毒例も報告されている。特異的療法および解毒剤はないが、各地の医療機関で中毒の治療研究が行われている」とあった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO2000)
|

|
9.クサギ(臭木)の実
クサギとは、枝や葉に悪臭があることから「臭木」の名がある。舞岡公園には何か所かクサギの木が生えているところがあり花が咲く夏には、黒いアゲハたちが吸蜜に来る。写真はその果実であり、赤い萼が鮮やかだ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 183mm ISO500)
|

|
10.レモン(檸檬)
檸檬の実はもっと楕円でラグビーボールのような形をしていると思っていた。前回はたしかダイダイと同定してしまっていたかと思う。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 45mm ISO400)
|

|
11.古民家の裏庭のフジバカマ(藤袴)
今年は少し咲くのが遅いように思う。ヒヨドリソウの仲間であり、同様に多くのチョウが集まってくる。アサギマダラの好物だ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 9mm ISO500)
|

|
12.熟したカキの実に来たキタテハ
もしかしてコムラサキでも吸蜜していないかと期待したが。はじめて舞岡公園でコムラサキを撮影したのは2012年6月だった。次に見たのは2015年9月12日だった。また、今年の5月17にはヤナギの木の周囲を旋回する2頭を目撃している。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 216mm ISO400)
|

|
13.黄金色の稲田
まだ、刈り入れが行われていない稲田は黄金色だった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 172mm ISO125)
|

|
14.ウラナミシジミ -1
谷戸の畦道に咲くコセンダングサ(小栴檀草)には、ウラナミシジミが数頭集まってきていた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 218mm ISO160)
|

|
15.ウラナミシジミ -2
翅を開いてくれた。♂と同定できる。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 218mm ISO160)
|

|
16.コスモス -1
狐久保に入るところの休耕田に、ヒマワリが終わると、コスモスの花が咲く。wikipediaを見ると、コスモス(学名:Cosmos)はキク科コスモス属の総称であるが、種としてのオオハルシャギク Cosmos bipinnatus Cav. を指す場合もある。アキザクラ(秋桜)とも言う。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 12mm ISO125)
|

|
17.コスモス -2
まっすぐ行くと北門で、左へ曲がると狐久保だ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 16mm ISO125)
|

|
18.イヌタデ(犬蓼)
wikipediaを検索してみると、「道端に普通に見られる雑草である。」との記述があった。まさに花も小さくて地味だし、雑草である。だが、雑草という名の草はないと言われる通り、イヌタデという名があった。赤い小さな花や果実を赤飯に見立て、別名アカノマンマともよばれるそうだ。"アカマンマは聞いたことがあるし、わかりやすい。「蓼食う虫も好き好き」ということわざがあるが、他に草があるにも係わらず辛い蓼を食べる虫も居るように、人の好みは様々で、一般的には理解しがたい場合もあるということをいう。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO400)
|

|
19.アキノノゲシ(秋の野芥子)
和名は、春に咲くノゲシ(ハルノノゲシ)に似て、秋に咲くことから付けられた。乳草、ウマゴヤシ、ウサギグサなどの別名があるそうだ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 214mm ISO250)
|

|
20.谷戸の風来坊
9月12日に舞岡公園に来た時も、この案山子はこの場所にあった。そこは瓜久保の家からかっぱ池へ行く途中の畑のわきだった。案山子コンクールの多くの作品が立っているところではない。だが、この日見ると「36番 谷戸の風来坊」という名前が付けられていた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.4 1/1250秒 9mm ISO320)
|

|
21.やとひとちゃん
こちらも9月12日に来た時に見ている。この作品には「35番 やとひとちゃん」という名が付けられている。この2つの作品は「NPO法人小谷戸」の里の竹細工指導員さんの作品なのだそうで、この時には案山子コンクールには参加していないと聞いていた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 11mm ISO250)
|

|
22.カラタチ(枳殻、枸橘)の実
和名カラタチの名は唐橘(からたちばな)が詰まったものだそうだ。9月に見たときより直径3-4cmのその実はより黄色く色づき、より大きくなっていた。それにしても立派なとげである。春には葉が出る前に3-4cm程の5弁の白い花を咲かせる。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 198mm ISO500)
|

|
23.ヒメアカタテハ
帰り道、畑の傍に咲くコセンダングサに飛来したヒメアカタテハに久しぶりにあった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 220mm ISO100)
|

|
24.キタテハ
このキタテハは秋型であることは間違いないが、まだ、その過渡期に生まれてきたような感じがする。キタテハもコセンダングサによく来る。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 216mm ISO125)
|

|
25.案山子
案山子コンクールは、9月16日(土)~10月15 日(日)の間、人気投票が行われ、人気投票で 1位~3位の作品には、賞品が贈られることになっていた。出展数38体 で総投票数は1,462票で、その結果は、この写真の中央が1位の益虫隊長カマキリダー!!(175 票)、その右側の22番が2位の舞岡スターマン(124 票)、左の24番が5位の田んぼの守り神(92 票)であったようだ。写真はないが、3位はスーパーマリおこめ(121 票)であった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 10mm ISO250)
|

|
26.ホトトギスに飛来したホウジャク
花弁の斑点が鳥のホトトギスの胸の模様に似ていることからホトトギス(杜鵑草)と名づけられた花が、日陰に咲いていた。その花にホウジャクが来てホバリングをしながら口吻を伸ばし吸蜜していた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 78mm ISO1250)
|

|
27.キツリフネ(黄釣船)
ムラサキツバメでもいないかと思い、足を踏み入れたことがない戸塚駅方面へのバス停の横の森に入って見た。ムラサキツバメは見つからなかったが、見たことのない黄色い花が咲いていた。「Picute This」で検索してみるとキツリフネとでた。葉の下から細長い花序が伸び、その先に3ー4cmほどの横長で黄色い花が釣り下がるように咲く。花弁状の萼と唇形の花びらをもち、距が長く筒状になっている。ツリフネソウに似ているが黄色い花が名前の由来になっているそうだ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO2000)
|