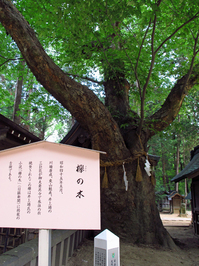快晴の上高地 ⑥ 2023年8月8日-10日 立山黒部アルペンルートとトロッコ電車・上高地3日間
8月10日、ツアー最後の日となった。今日は上高地へ行く。上高地へは3週間前の7月17日に、一人で日帰りで来ており、その時は天候が優れず、チョウの写真も撮れなかった。今回はリベンジしたいのだが。
朝は気持ちよく晴れていた。上高地で3時間の散策時間をとるために、朝は7時30分の出発となった。白馬からリンゴの果樹園の中を走る「北アルプスサラダ街道」を走った。安曇野から松本の市街は通らず、気が付いたら新島々の駅前に出ていた。
途中、道の駅「風穴の里」でトイレ休憩をとって、あとは、いつもの上高地への道を走る。
上高地には10時少し前に着いた。文句のつけようがない快晴である。車窓からも吊り尾根が見えた。いつもは大正池から歩くのだが、今回はバスターミナルまで乗っていってしまうことにした。小梨平で写真を撮りたい。バスを降りると涼風が爽やかだった。

文句のつけようがない快晴の穂高連峰 2023年8月10日 上高地 河童橋付近から

|
90.白馬のホテルを出発 快晴の涼しい朝だった。7:30に出発の予定だったが、全員5分前には揃っていて、上高地に向かって出発した。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/1250秒 12mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|
91.高瀬川を渡る(車窓から) バスは長野県道308号線を南に走る。青木湖、木崎湖を右に見て走る。大町を過ぎたあたりで高瀬川を渡る。松川地区の国営アルプス安曇野公園の近くを走る。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/1250秒 12mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|
92.北アルプスサラダ街道(車窓から) 国営アルプス安曇野公園のあたりからしばらく走ると、道路わきに「北アルプスサラダ街道」という表紙が立てられたのどかな道を走っていた。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|
93.リンゴ畑(車窓から) 実が大きくなり始めたリンゴ畑が両側に見える。北アルプスサラダ街道は安曇野市から長野県道25号塩尻鍋割穂高線を走る長野県松本地域西部にある観光道路であり、野菜や果物栽培が盛んな市町村を結んでいる。wikipediaによれば、1988年より取り組みが始まり、大規模なハード事業による観光開発をしないで、日常の農村を味わってもらうことが趣旨となっていた。日本アルプスサラダ街道協議会主催で街道ウォークなどのイベントが行われていたそうだ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|
94.新島々駅(車窓から) バスは松本市内に入らず、安曇野からサラダ街道を走り、松本電鉄上高地線に並行して走る国道158号線に突き当たる。そこを右折し、見慣れた新島々の駅前に出た。後は上高地まで3週間前にもバスで通った道である。松本から出ている、かつて松本電鉄上高地線といわれた、現アルピコ交通上高地線の終着駅である。ここからバスに乗り換えて上高地へ入ったこともあった。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|
95.道の駅「風穴の里」 新島々から上高地へ行く途中、唯一のPAである道の駅で一休みした。出発してから2時間近く経っている。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|
96.梓湖(車窓から) 梓川の奈川渡ダム堰止湖である。槍ヶ岳に源を発し南流する梓川は上高地で大正池を形成し、梓湖(奈川渡ダム)に注ぐ。国道158号線はこの奈川渡ダムの堰堤の上を走る。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/1250秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|
97.奈川渡ダム 安曇発電所(車窓から) それまで梓川にはダム式発電所がなかったが、1969年(昭和44年)11月に、奈川渡ダム、水殿ダム、稲核ダムの梓川3ダムが完成した。中でも奈川渡ダムは、長野県で1番大きなダムであり、高さ155mのアーチ式コンクリートダムで、日本のアーチダムの中でも3位の堤高を誇る。2010年の5月だったか、学生時代の同期の体育会の仲間との旅行の折、友人の東京電力に務めるM氏の尽力で、この奈川渡ダムおよび発電所を見学させてもらったのを覚えている。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/1250秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|
98.トンネルを抜けて上高地へ(車窓から) バスはトンネルを抜けて上高地に入った。車窓から穂高連峰の吊り尾根が、遮る雲なく見えた。思わず目を見張る。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 13mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
99.焼岳 大正池の次に、上高地帝国ホテル前で何人か下車する人たちがいて、最後に上高地バスターミナルまで乗っていったのは、私たち2人を含めてほんの数人であった。集合時間を確認して、出発する。長野県と岐阜県にまたがる標高2,455 mの活火山、焼岳を眺めると、山肌が荒々しかった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 13mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
100.穂高連峰と河童橋 吊り尾根の上は雲一つない。吊り尾根の右側に前穂高岳3,090m、左側には奥穂高岳3,190mがそびえる。この眺めで3週間前の雪辱を果たせた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
101.ロバの耳、ジャンダルム 奥穂高岳から左へ、馬の背、ロバの耳、ジャンダルムと呼ばれる峰々が連なる。ジャンダルム (Gendarme) は、奥穂高岳の西南西にあるドーム型の岩稜で標高は3,163 mある。wikipediaによれば、名称はスイス・アルプス山脈のアイガーにある垂直の絶壁(高さ約200 m)の通称に由来するが、本来はフランス語で国家憲兵のこと。転じて山岳用語としては、尾根上の通行の邪魔をする岩をいう 。奥穂高岳ジャンダルムは奥穂高岳の前衛峰として名付けられた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 27mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
102.河童橋のたもとから 我ながら良いアングルを見つけたと思う。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
103.キオン 岳沢温原の方へ行ってみようと思い、河童橋を梓川右岸に渡る。明神池の方に向かって歩き始めると、ホテルの裏側の空き地に黄色い花が咲いていた。キオンだ。何やらヒョウモン蝶が来ているが、遠くてよくわからない。
Nikon D5300 TAMRON 90mm f/2.8 VR S シャッタースピード優先オートで撮影 ( f8 1/1000秒 90mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|
104.キオンに来ていたオオウラギンスジヒョウモン 写真右下の方に花に隠れてオオウラギンスジヒョウモンの姿が見える。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/640秒 114mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
105.ツマグロヒョウモン♀ 道に止まったチョウはツマグロヒョウモンだった。上高地でツマグロヒョウモンとは。こんな高地にも進出してきている。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/800秒 160mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
106.熊目撃情報 岳沢湿原への道に「熊目撃情報」の看板が立てられていた。「8月10日 午前9時50分 現在地付近 ツキノワグマ1頭」と書かれている。この写真を撮ったのは、8月10日 午前10時30分 ある。つい40分前にいたということだ。クワバラクワバラ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3,5 1/500秒 24mm ISO2500 ) 露出補正 なし |

|
107.コムラサキ -1 上高地ではコムラサキを多く見る。この個体は、裏面の色がすこし濃いように思う。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4,5 1/1000秒 152mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
108.コムラサキ -2 少し翅を開いてくれた。♀のようだ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4,5 1/1000秒 220mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|
109.絶景 7月の終わりごろに岳沢では、タカネキマダラセセリ、クモマツベニヒカゲという憧れの高山蝶が発生する。一度は行ってみたいと思っていた。岳沢 は、上高地の河童橋などから正面に見える穂高連峰の中腹にある渓谷で、上高地内のハイキングだけでは物足りない人にお薦めの軽登山コースと紹介されている。最高地点の標高は2170mで、上高地から2時間半かかるそうだ。とても横浜からの日帰りでは無理である。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3,5 1/500秒 32mm ISO100 ) 露出補正 なし |