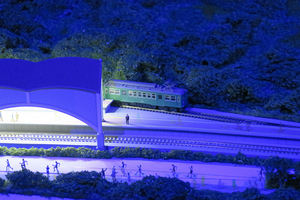セレモニーが終了すると、各車はゼッケン番号順に列を作り、10時30分のスタートを待つ。ゼッケンは80番まであったが、そのうち、4番、9番、42番は欠番で、2番に予定されていたAUSTIN SEVENと、65番ポルシェ911Sはどうやら出走を取り止めたようだ。
先導車に続き、正確に10時半に、今回出場した車の中では最も古い、ゼッケン1番の1927年式、BUGATTI T-35Bが山下ふ頭をスタートして行く。山下公園通りを走り抜け、山中湖へ向かった。21番に雅楽演奏家の東儀秀樹さんの愛車が紹介され、ご子息をナビゲータにしてスタートしていった。
すべての名車のスタートを見届けて、山下ふ頭を後にし、山下公園を歩く。山下公園では今年もベルギービール ウィークエンドという催しが行われていた。歩きながら、大桟橋のほうを眺めると、大きな客船が入っていた。ちょっと見ていくことにする。この船はイタリア・ジェノバ船籍のCOSTA NEO ROMANTICA 53,049総トン だった。
24.スタートを待つ名車
RALLY YOKOHAMA 2018 は10時半に山下ふ頭をスタートしていく。各車スタートのスタンバイをしている。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 41mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
25.横浜観光親善大使
先導車には、平成30年度(第16代)横浜観光親善大使の榊原里江さん(左)と本行慶子さん(右)の2人が乗る。(横浜観光情報http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/tourism/shinhakken/)
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 60mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
26.先導車のポルシェ911
先導車はまだ新しい真っ白なポルシェだった。この車はポルシェ 911 カレラ ガブリオレというのだろか。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/640秒 26mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
27.先導の県警白バイ
10時15分、先導する神奈川県警の白バイに続き、ゼッケン番号順にスタートする車が列を作って準備している。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 34mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
28. ブガッティ-35B(1927年式) スタート
10時30分、フラッグが上げられ、ゼッケン番号1番の ブガッティ-35B(1927年式) がスタートしていった。スタート正面で30数名近くいたカメラマンに交じって撮影した。私の目の前で右に曲がって山下公園通りに出ていく。エンジン音が響く。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 84mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
29.ラゴンダ LG45 (1936年式)
ゼッケン番号2番のオースティン セブンが出走取消だったので、次にスタートしたのは、イギリスの高級車といわれるラゴンダ LG45だ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 81mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
30.ラリー N.C.P (1931年式)
ゼッケン番号4番、9番、42番は日本的に欠番にされていたので、3番目のスタートは、ゼッケン番号5番のRALLY N.C.P。クラシック・カーらしくて、色も良い。後日、ラリーの結果をホームページで見たが、この車が第3位に入っていた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 81mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
31.フィアットバリラ スポーツ 508 S (1934年式)
ゼッケン番号5番のFIAT BALLILA SPORTS 508 S。このクラシック・カーと言うにふさわしい車はライトブルーを基調にしたツートンカラーが美しかった。FIATのホームページには、このころイタリアはムッソリーニの独裁体制の下で、フィアットは海外事業の縮小を迫られ、国内市場に専念する。1930年代に入るとトラックと商用車が大きな技術発展を遂げ、航空・鉄道部門も発展したとある。 現在、街を走るフィアット500 は小粋な車だ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 81mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
32.ベントレー マーク V1 スペシャル (1950年式)
BENTLEY MK VI はベントレーが1946年から1952年に製造した乗用自動車である。 wikipediaによると、ロールス・ロイスはベントレーを吸収した後、ベントレーを「小型ロールスに幾分スポーツカー的な要素を加えたモデルをオーナードライバー向けとして販売するブランド」と位置づけるようになり、この方針は第二次世界大戦後も踏襲された。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 37mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
33.ラゴンダ V12 (1939年式)
ゼッケン番号14番、LAGONDA V12 の エンジンは12気筒V型で200馬力だそうだ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 172mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
34.東儀さんのACエース(1954年式)がスタート
ご子息をナビゲータに、東儀秀樹さんの AC ACE が颯爽とスタートしていった。このラリーに出場した車は、わたくしが数えたところ75台だと思う。うち、11台がリタイアしたが、その中で、このACエースはラリーの全体4位に入る好成績だったようだ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 140mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
35.MG A (1956年式)
一般的にはMGは元々、「モーリス・ガレージ」(Morris Garages )を略したものであるとされている。現在は、中国上海汽車傘下だそうだ。 MG AはMGの主要車種の一つ。 今回 ゼッケン23のこの車は、堂々ラリーの2位になった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 140mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
36.アルファロメオ ジュリエッタ スパイダー (1957年式)
RALLY YOKOHAMA 2018 を制し、優勝したのは、このゼッケン27のALFA ROMEO GIULIETTA SPIDERだった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 178mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
37.マツダ ファミリア プレスト ロータリー クーペ (1970年式)
ゼッケン33の MAZDA FAMILIA PRESTO ROTARY COUPE は奥様をナビゲータにして、元気にスタートしていった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 42mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
38.ダットサン フェアレディー SPL212 (1960年式)
私が高校3年生のころ生まれた DATSUN FAIRLADY SPL212。なにか見覚えがある車のように思う。ダットサンという名が懐かしい。脱兎のごとく走って欲しい。なお、ダットサン(Datsun)は、日産自動車が2013年より新興国向けの低価格ブランドとして展開している自動車ブランドでもある。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 60mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
39.ジャガー MKⅡ (1963年式)
wikipediaによれば、第二次世界大戦後スポーツカー/グランツーリスモ及び大型サルーンのみを生産してきたジャガーが、新たな市場の開発のために1956年に送り出した ジャガー MKⅠ、MKⅡ、は小型の2.4サルーンであった。1959年10月に登場した JAGUAR MKⅡ はもちろんMKⅠの改良版であるが、ほとんど変わらない外見と異なり、メカニズム的には大きな進歩を遂げており、当時の世界の小型セダン市場に大きな衝撃を与えたのだという。 JAGUARは、アメリカ風の発音だと「ジャグワー」でイギリス風だと「ジャギュアー」と発音するそうだ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 76mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
40.フェラーリ 250GTE 2+2 (1962年式)
ゼッケン52番、Ferrari 250GTEは、イタリアの自動車メーカー、フェラーリが1960年から1963年にかけて生産した自動車である。エンジンは 2.953cc 水冷V型12気筒SOHCで、当時世界最速の2+2といわれたそうだが、思ったよりおとなしいデザインという印象を持った。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 56mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
41.フィアット 124 スポーツ スパイダー (1966年式)
1966年秋のトリノ・ショーにピニンファリーナのデザイン・車体製作による2ドアスパイダー(形式:124AS)が登場し発売された。 このFIAT 124 SPORT SPIDER はライバルと目されるアルファロメオ・スパイダーに比べて操作性に癖がないため、スポーツカー然とした見た目とは対照的に、大衆車メーカーならではの堅実な設計によって高い実用性を有している。(wikipediaを参照)
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 90mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
42.アルファ ロメオ スパイダー (1968年式)
スパイダーは、イタリアの自動車メーカー・アルファロメオが1966年から製造している2ドア・オープンカーである。 1968年には1,290cc 89馬力のスパイダー1300ジュニアが追加された。マリンタワーを背景にスタートしていく。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 21mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
43.ロータス セブン (1969年式)
ゼッケン番号64のロータス・セブン(Lotus Seven)は、イギリスのロータス・カーズがかつて生産・発売していたスポーツカー。1957年から1970年代にかけて生産、販売されていた。深緑に塗装され、きれいに磨かれた車体が颯爽と出走していった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 58mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
44.ジャガー E-タイプ シリーズⅢ (1973年式)
ゼッケン番号77、残っている車も少なくなってきた。 1961年にジュネーブモーターショーにて発表されたEタイプは、その美しいボディーラインのみならず、当時としては夢のような最高時速240km/hを誇り自動車界に一大センセーションを巻き起こしたという。1968年に外観を変更しシリーズⅡとなり、1971年に6気筒エンジンを12気筒エンジンに変更し、JAGUAR E-TYPE SR.Ⅲに発展させたEタイプは1975年まで生産されている。60年近く前に造られた車が時速240kmとは驚きである。レモンイエローの車体がまぶしい。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 28mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
45.しんがりのBMW 3.0 CSI (1974年式)
ゼッケン番号80番、今回エントリーされていた最後の車である。このBMWは2,985ccのエンジンに燃料噴射装置をが組み込むまれたインジェクション・モデルのようだ。後部ドアの窓が大きい。さて、75台(多分)のクラシック・カー、そしてオーナーのみなさんは、山下公園通りから、相模原の服部牧場でランチをとり、この日は山中湖のホテルに宿泊する。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 28mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
46.神奈川県警パトカー
そして、最後に神奈川県警のパトカーがフォローしていく。ゼッケン番号1番のブガッティがスタートしてから、約20分間、RX10M4で撮影を楽しんだ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 28mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
47.海上保安庁巡視船 「ざんぱ」
すぐそばの山下ふ頭1号岸壁に停船していた海洋保安庁の巡視船が、しんがりのBMWがスタートしたあと、ボーと汽笛を鳴らして離岸していった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 65mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
48.山下公園 「ベルギー・ビール ウィークエンド」
RALLY YOKOHAMA 2018 に集まっていた関係者や、写真を撮っていた多くの愛好家が、山下ふ頭から帰っていく。私は、帰りは日本大通りから帰ろうと思い、山下公園のほうへ歩いていった。山下公園の元町寄りの広場では、今年も 「ベルギー・ビール ウィークエンド」 が開催されていた。まだ、時間が早いので飲んでいる人も少ない。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 15mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
49.山下公園は花がいっぱい
氷川丸とHOTEL NEW GRANDに囲まれた公園には、 190品種、2300株 バラをはじめ、いろいろな花が咲いていた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 15mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
50.ガーデン・ネックレス横浜
3月24日から6月3日の間、ガーデン・ネックレスという横浜を花と緑が彩る催しが行われている。ここ山下公園をはじめ、港の見える丘公園、汽車道、日本大通り、横浜公園、赤レンガ倉庫のある新港中央広場など、花々がネックレスのように彩る。山下公園では、バラに多種類の草花を加え、連続するタワーやアーチによる立体的なバラ園が造られていた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 15mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
51.氷川丸
係留されている氷川丸も花に包まれているようだ。外国人観光客が写真を撮っている。「かもめの水兵さん」の歌碑が見える。 「かもめの水兵さん」 は1937年(昭和12年)にレコード化された童謡で、レコード化以来、多くの子供達に好かれて謳われている。石碑には歌詞や説明文が明確に刻まれていた。 1979年(昭和54年)11月に建てられている。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 15mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
52.大桟橋
山下公園を歩きながら大桟橋のほうを眺めると、大型客船が停泊していた。ちょっと、足をのばして見に行ってこよう。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 42mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
53.象の鼻から大桟橋へ
船は以前(2014年)に見に来た「クイーン・エリザベスⅡ」に比べると、それほど大きくはないようだ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 38mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
54.「COSTA NEO ROMANTICA」船尾
船の名前は「 コスタ・ ネオ・ロマンチカ」、イタリアはジェノバ船籍である。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 16mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
55. 「COSTA NEO ROMANTICA」船体
イタリアのジェノヴァに本社を置く、クルーズ客船運航会社の客船で、1993年に建造された。全長221m、総トン数は53,039トンと今でこそ、そう大きくはないが、当時は最大級の客船だったのだと思う。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 19mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
56.スマホに目を落とす船員さん
「東京横浜発着 コスタ ネオ ロマンチカ号で行く済州島・九州ロマン紀行」という6泊7日のツアーで、 この船は5月13日に東京晴海ふ頭を出航し、神戸、済州島、鹿児島に寄港して、この日5月19日に横浜に着いた。この船員さんは上級スタッフだろう。白髪が似合う。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 178mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
57.船首
「コスタ ネオ ロマンチカ」は、明日はプサンに向け出航していく。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 14mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|