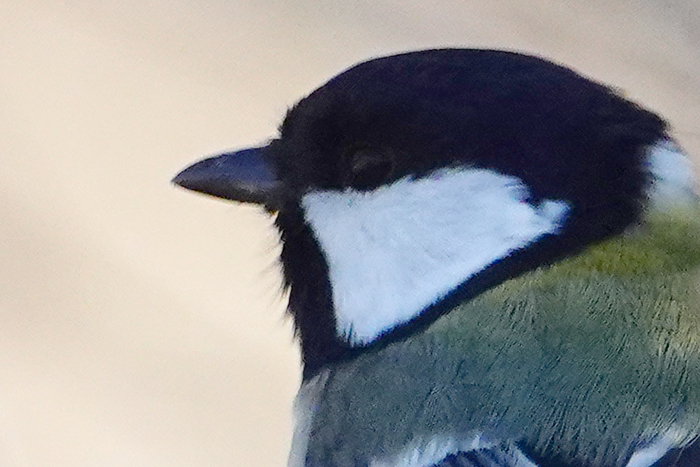|
1.ヤマツツジ
昨年来た時もヤマツツジが咲いていた。傍にいた公園を管理されてる方に訊ねてみると、「先週から咲き始めました」ということだった。ということは昨年とほぼ同じ状況ということか。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 44mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
2.ミツバウツギ
ミツバウツギの蕾が開きかけていた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
3.コミスジ
ミスジチョウかと期待したが、コミスジだった。でも、きれいな個体であった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
4.フジ(藤)
フジの花が咲いていた。フジなのか、ヤマフジなのかはわからなかった。wikipediaを検索するとヤマフジについて「なお、フジの野生品、あるいは山にあるフジ、ということでフジのことをヤマフジという事例があり、ネット上ではそのような誤用が結構見られるので注意を要する。」という記述があった。フジとヤマフジの違いとしては、フジではつるは左巻き、成葉はほぼ無毛であるのに対して、ヤマフジではつるは右巻きというが、写真ではわからない。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO800 ) 露出補正 なし
|

|
5.クロヒカゲ
山地性のチョウである。ここでは個体数は少ない。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO1600 ) 露出補正 なし
|

|
6.ウスバシロチョウ -1
アオバセセリのポイントまで行ってきて、再びハルジオンが咲くところへ戻ってきた。11時近くになり、翔ぶウスバシロチョウの数が増えてきた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO125 ) 露出補正 なし
|

|
7.ウスバシロチョウ -2
次々とハルジオンの花に来ては吸蜜を始める。ここでは安定して個体数は多い。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
8.ウスバシロチョウ -2
薄紫のハルジオンで吸蜜する。♀のようだ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.0 1/1000秒 105mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
9.ベニシジミ -1
ベニシジミの春型は、前翅一面のオレンジ色が鮮やかで、ことさら可憐な蝶である。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f3.2 1/1250秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
10.ベニシジミ -2
カメラをマクロに持ち替えて撮った。ポートレート的にきれいに撮ってあげられたと思う。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.6 1/1000秒 105mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
11.ムラサキシジミ 越冬個体
何が翔んできたのかと思ったらムラサキシジミだった。ムラサキシジミは年に3回ほど発生するが、晩秋に羽化した個体は越冬し5月まで飛んでいる。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO500 ) 露出補正 なし
|

|
12.ミツバウツギに来たウスバシロチョウ
路傍に咲くミツバウツギにウスバシロチョウが飛来した。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 186mm ISO250 ) 露出補正 なし
|

|
13.クモガタヒョウモン♂開翅
昼近くになって、クモガタヒョウモンが活発に飛びまわる姿が見られるようになった。この日翔んでいたクモガタヒョウモンはすべて♂だった。前翅には、はっきりとした性標が見られる。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
14.クモガタヒョウモン -1
正面に向き合った。目がクリクリとして精悍である。実は、あまりよく見えていないようだ。昆虫の目は複眼で、視力は0.01以下しかないという。 さらに眼の構造上、私たちのようには立体視ができない。 目が悪くて、立体視もできないような世界でありながらも、飛んでいる虫を自分も飛びながら捕らえ、障害物をサッと避けることができるのだ。触覚や聴覚など、優れた高感度センサーを身体中にまとい、そこから得られる情報をできる限り分散脳で処理し、環境の変化に迅速に対応できるようにしたのだという。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO200 ) 露出補正 なし
|

|
15.クモガタヒョウモン -2
クモガタヒョウモンの後翅裏側は本種特有のオリーブ色である。ヒョウモンの仲間で裏面の模様がほとんどないのは本種のみ。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
16.クモガタヒョウモン -3
春になって最初に見るのはツマグロヒョウモンだが、このクモガタヒョウモンも他のヒョウモンチョウより早く、5月中旬から出現するという。まだ、4月末である。やはり、今年は発生が早いのだろう。暑さを避けて「夏眠」するので、真夏にはいったん姿を消し、秋に再び現れる。その時は損傷した個体が多い。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO160 ) 露出補正 なし
|

|
17.クモガタヒョウモン -4
吸蜜していたハルジオンの花から飛び立つ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.0 1/1000秒 105mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
18.ウスバシロチョウ -3
1週間ほど前に訪れた武蔵嵐山でも多くのウスバシロチョウを見た。近年、ウスバシロチョウの発生時期も早くなっているようだ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 105mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
19.カラスアゲハ♀
渓谷沿いに咲くミツバウツギの花にカラスアゲハが来ていた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO1600 ) 露出補正 なし
|

|
20.オナガアゲハ♂ -1
地表近くに咲くクサイチゴの花でオナガアゲハが吸蜜していた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 218mm ISO320 ) 露出補正 なし
|

|
21.オナガアゲハ♂ -2
開翅したところを撮れた。♂の特徴である後翅前縁の白斑が見える。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 218mm ISO320 ) 露出補正 なし
|

|
22.クモガタヒョウモン -5
♀を撮りたいと思ったが、まだ発生していないようだ。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f5.0 1/1000秒 105mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
23.ウスバシロチョウ -4
吸蜜に忙しい。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f2.4 1/1250秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
24.オナガアゲハ♂裏面
後翅裏面の橙色の模様が美しい。♀はもっときれいなのだが。クロアゲハに比べて翅が細い。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO1250 ) 露出補正 なし
|

|
25.オナガアゲハ♂ -3
この個体は長い間ハルジオンの花の周りを翔び、翅に花粉を付けていた。吸蜜する花を換えていた。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO3200 ) 露出補正 なし
|

|
26.オナガアゲハ♂ -4
この個体はしばらく離れないで、私の相手をしてくれていた。
Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1000秒 105mm ISO100 ) 露出補正 なし
|

|
27.オナガアゲハ開翅
翔び疲れたのだろうか、葉の上に翅を広げてベッタリと止まった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO3200 ) 露出補正 なし
|

|
28.ウスバシロチョウ開翅
ウスバシロチョウもまた近くの葉の上に止まり、羽を開いて休んでいるようだ。昼前の姿とは違う。2時半になった。本命のアオバセセリには会えなかったが、新鮮なクモガタヒョウモンと翅に傷のないオナガアゲハを撮影できたのは良かった。
SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels
シャッタースピード優先で撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO320 ) 露出補正 なし
|