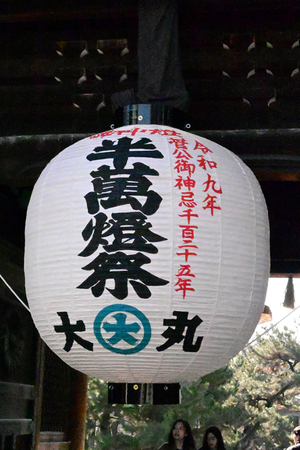|
1.「菓子屋横丁」入口
バスを札ノ辻で降り、交差点を西へ歩く。しばらく行くと左手に「これより菓子屋横丁」という表示があったが、ここは左に入らずにまっすぐ進む。。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 9mm ISO125 )
|

|
2.「菓子屋横丁」の案内図
案内図にある焼き団子の「池田屋本店」などの前を通ってこの案内図のところに出た。ここから左へ入る。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 9mm ISO125 )
|

|
3.「菓子屋横丁」
カルメ焼きの「吉仁製菓」と、川越名物「小江戸蔵まんじゅう」の店の間の横丁をまっすぐ北へ進む。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 9mm ISO125 )
|

|
4.「大黒棒 (麩菓子)」
横丁が突き当たる手前の左側の店先に「大黒棒」というのが並べられていた。ここは小江戸茶屋という駄菓子屋さんだ。ホームページには、「昔懐かしい駄菓子から、サツマイモを原料としたお菓子はもちろんのこと、遊び心溢れたとても長い麩菓子「大黒棒」を川越菓子屋横丁で初めて販売開始。今では数種類の長い麩菓子が川越のあちらこちらで見かけるようになり、川越菓子屋横丁の風物詩になりました。」と書かれていた。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 9mm ISO125 )
|

|
5.風情のある建物
大黒棒の店の角を左に曲がる。蔵造りではないが古い木造の店が並ぶ。左側に「彩香」という漬物と菓子の店、その向こうに昔の技を今に伝えるという組みあめ「玉力製菓」、右側には麩菓子の「松陸」、ベーゴマも売っている芋菓子「よしおかYA」、手作りの飴玉各種「松本製菓」、川越わらび餅などの「菓匠右門」と、さすが菓子屋横丁というだけある店が並んでいた。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 21mm ISO160 )
|

|
6.新しい店
突き当りを左へ行くと、店内の照明も明るい新しそうな菓子店があった。2人の女性が店の前で客を招き入れていた。今年の2月にここに川越店としてオープンし、同じ名称の店が2023年11月に京都伏見にオープンしている。川越に8店舗を持つ、株式会社寺子屋という土産物を販売する会社の経営だそうだ。2.の写真の菓子屋横丁案内図にはない。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO125 )
|

|
7.「川越まつり会館」の裏手
菓子屋横丁を出る。これから行く川越蔵造りの街並みの通りに川越まつり会館がある。菓子屋横丁の蔵造りの街並み(一番通り)と並行する菓子屋横丁の側(寺町通り)からその後ろ側を見たところだ。毎年10月の第3土日に行われる川越まつりの山車の収納庫があるようだ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 37mm ISO125 )
|

|
8.「蔵造りの街並み」 北側の始まり
札ノ辻の交差点に戻り、右(南)へ。ここから一番街の蔵造りの町並みが始まる。小江戸川越ウェブというサイトには、「江戸時代、川越藩主松平信綱の町割りによって、通りに店が向かい合う形の家並みができあがったが、度重なる大火のため幕府がかわらぶきを奨励し、火事に強い建物として江戸の町で土蔵造りが流行した。これによって商業で江戸と結び付きが強かった川越でも、蔵造りの商家が建つようになった。 現在の蔵造りの多くは、川越大火後に建てられたもので、今も30数棟が残る。大正12年、関東大震災やその後の戦災によって東京の蔵造りが姿を消したこともあり、江戸の景観を受け継ぐ重要な歴史的遺産として、「時の鐘」をはじめとするこの一番街周辺は、平成11年12月1日に重要伝統的建造物群保存地区に選定された。」と説明されている。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 30mm ISO125 )
|

|
9.「大澤家住宅」
南に向かって歩き始めてすぐに、左側に「大澤家住宅」があった。今は「小松屋」という屋号だが、店内は江戸時代の呉服屋のおもむきを残している。 和小物を中心に山車のミニチュア、時の鐘ストラップ等 川越の民芸品の店である。まだ開店前の店の中を覗き込む観光客の姿があった。wikipediaによれば、この蔵造りの建物は、寛政4年(1792年)の建造で、の川越大火(1893年)の焼失を免れた川越最古の蔵造りで、現存する関東地方最古の蔵造りでもある。国の重要文化財の指定を受けている。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 18mm ISO200 )
|

|
10.路地 建物の壁
路地があって、その建物の壁が印象に残った。これは出格子(でごうし)または千本格子と呼ばれる伝統的な建築様式の一種で、特に川越の蔵造りの町並みでよく見られるものだそうだ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 16mm ISO125 )
|

|
11.「時の鐘」付近
川越のシンボルである「時の鐘」は蔵造りの街並の一番街の通りには面していない。大澤家住宅のちょっと先を左に入ったところの左側にある。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 37mm ISO125 )
|

|
12.蔵の街にも
蔵の街にもこんな店があった。川越を観光する人たちは、若いお嬢さんがたも多い。写真で見ると、この店は、川越に8店舗ある株式会社寺子屋さんの「みっふぃーベーカリー」のようだ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 11mm ISO125 )
|

|
13.「蔵のキッチン&ベーカリー」
お店には「みっふぃー蔵のキッチン&ベーカリー」と書かれた看板が掛けられていた。これも、これからの蔵の街での生き方だ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2 1/1250秒 11mm ISO125 )
|

|
14.店じまい
「明治・大正・昭和・平成・令和と長きにわたり、あきないを続けてまいりましたが、高齢の為、令和六年十二月末日にて店を閉じることにいたしました。今までのご愛顧を心から感謝申しあげますと共に、ご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。」という張り紙がされていた。「松岡種苗店」という種子屋さんの、歴史が沁み込んだ貫禄のある立派な板の看板である。中を覗いてみると、まだ、商品の種の袋などが並んでいた。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO320 )
|

|
15.「時の鐘」
通りの右側に「川越まつり会館」がある辺りを左に入ると、「時の鐘」が現れた。wikipediaによると、「川越の蔵造りの街並みを代表する観光名所で市のシンボルとなっている。地元では鐘撞堂(かねつきどう)と呼ばれることが多い。3層構造の塔で、高さは16m。古くは鐘撞きが決まった時間に時を知らせていたが、現在では自動で1日4回(午前6時、正午、午後3時、午後6時)川越城下に時を知らせている。」と解説されていた。前の道が広くないので、全体を入れて撮る構図が難しい。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 9mm ISO125 )
|

|
16.「薬師神社」
「時の鐘」の塔をくぐって中に入ると、「薬師神社」の境内になっていた。神社は病気平癒、特に眼病に対してご利益があるとされる。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 37mm ISO125 )
|

|
17.「時の鐘」の鐘
「薬師神社」の境内から「時の鐘」の塔を眺めると、鐘と撞木(突き棒)が見えた。wikipediaによれば、江戸時代の寛永年間に川越藩主・酒井忠勝によって建設されたのが始まりであるが、火災によりたびたび焼失しており、1654年(承応3年)正月には川越藩主の松平信綱が椎名兵庫に命じて新たな鐘を鋳造させたといわれる。現在の鐘楼は4代目で、1893年(明治26年)に起きた川越大火の翌年に関根松五郎の設計で再建されたものである。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 30mm ISO125 )
|

|
18.「陶舗やまわ」
「時の鐘」の路地を出て、蔵造りの街並みの通りに戻る。「陶舗やまわ」という暖簾の下がった大きな蔵造りの店があった。陶舗やまわの店蔵は、川越大火後の明治26年に建てられ、現存する入母屋形式の土蔵造りとしては日本で最大級の規模だそうだ。「陶舗やまわ」として営業している建物は、もともと「原家」の商家住宅だった。通りから見る店蔵には5っの重厚な観音開きの窓が見える。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250 14mm ISO125 )
|

|
19.「陶舗やまわ」 大きな屋根の上
「陶舗やまわ」を右に廻って南側から眺めると、軒蛇腹の上に大きな千鳥破風が見える。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2 1/1250秒 10mm ISO125 )
|

|
20.「陶舗やまわ」 大きな鬼瓦
「陶舗やまわ」の屋根には、その角に大きな鬼瓦があった。鬼瓦は魔除けや火除けの意味を込めて設けられる。特に商家や寺社仏閣に見られ、家の繁栄と安全を願う縁起物でもあるそうだ。この「陶舗やまわ」 の大きな鬼瓦は非常に精巧で、圧倒される。瓦職人の高度な技術が使われており、川越の蔵造りの町並みにふさわしい格式と意匠美が表現されている。「陶舗やまわ」は、陶器商として栄えた原家が大正時代に建てた店舗であり、鬼瓦にも当時の商家の繁栄と威厳を示す意味が込められているという。関東大震災以降に防火を意識した蔵造りの建築が復興の象徴となり、川越の町並みに調和するよう設計されたそうだ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 17mm ISO160 )
|

|
21.「日蓮宗 行傳寺」
路地の先には「行傳寺」というお寺が見えた。川越にはお寺が多い。川越は江戸時代に小江戸と呼ばれ、川越藩の城下町として栄え、城下町では幕府の当時を安定させる目的で、寺社の建立が奨励されていたそうだ。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 37mm ISO125 )
|

|
22.「りそなコエドテラス」
蔵造りの町並みを3分の2ほど歩くと、ひときわ目立つ3階建ての洋風の建物が現れた。ここは埼玉りそな銀行の前身銀行の一つである旧第八十五銀行本店として、1918年に現在の場所へ移転新築された。1996年に国の登録有形文化財として埼玉県で第1号の登録を受け、2023年で築105年の建物だそうだ。老朽化に伴い2020年6月に支店としての営業を終え、修繕工事を経て、コエドテラスがGRAND OPENした。ちなみにりそな銀行の前身は、大和銀行とあさひ銀行である。2003年3月に、大和銀行とあさひ銀行が合併し、りそな銀行となった。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 21mm ISO125 )
|

|
23.旧頭取室
りそなコエドテラスの中に入ってみた。1階はレストランなどがあって、2階に上がると、蔵造りの街並に面した角に旧支店長室があった。この建物で最も良い位置だと思う。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO800 )
|

|
24.マサキ(柾、正木)
りそなコエドテラスのテラス席(展望台)から蔵造りの町並みを見下ろした後、建物の外に出た。建物の後ろ側に、見慣れぬ黄色い花が咲いていると思って近寄って見ると、花ではなく葉だった。後でPictureThisで検索してみると、それはマサキの葉だった。若葉は白っぽく、成長するにつれて明るい黄緑色になる。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 12mm ISO125 )
|

|
25.「法善寺」
時刻は10時50分。そろそろ腹が空いてきた。りそなコエドテラスを出て「大正浪漫夢通り」へと歩く。そのすぐ左側の路地の先に法善寺というお寺があった。この寺は真宗大谷派寺院の法善寺といい、もとは真言宗寺院として丹波国氷上郡にあったが、寛正元年(1460年)に法印良應が当地へ移し、その後浄土真宗に改めたという。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 27mm ISO125 )
|

|
26.日本初電気ボンネットバス
目の前を見慣れぬバスが通った。「小江戸巡回バス」だ。カメラが追い付かず、そのボンネットは撮れなかったが、後ろの窓に日本初電気ボンネットバスと書かれていた。調べて見ると、このバスは、イーグルバス株式会社が、中国製の電気バスをベースに日本で改造したオリジナルモデルだという。日本で走る電気ボンネットバスとしては「初」なのだろうが、「日本初」と謳うのはちょっとおこがましいような気がする。
Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels
プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 9mm ISO125 )
|